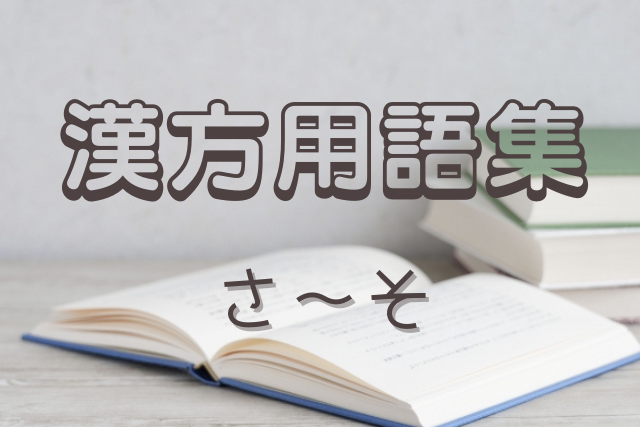|
思(し)
|
|
思う・考えること。生体に影響をおよぼす七情のひとつ。過剰に思い悩みすぎると気を滞らせて脾が弱る。腹痛、動悸、不眠、食欲不振などが起こることがある。
|
|
支飲(しいん)
|
|
肺や心下部に水飲が貯留し、肺の宣発・粛降を妨げ、咳嗽、呼吸困難(起坐呼吸)、浮腫が生じる。肺水腫。
|
|
滋陰(じいん)
|
|
陰液を養う薬を用いて、主に陰虚証を改善させる。補陰。参照⇒補陰薬
|
|
自汗(じかん)
|
|
自然に出る汗。日中、特に激しい運動をしなくても汗をかきやすい。気虚や陽虚によることが多い。
|
|
四気(しき)
|
|
生薬の、体を温めるか冷やすかによる分類。熱性・温性(・平性)・涼性・寒性。
|
|
直中(じきちゅう)
|
|
邪が表から裏に侵入したのではなく直接裏を障害すること。太陽病からではなく三陰病から発症すること。
|
|
歯痕(しこん)
|
|
歯痕舌。舌の両側に歯のギザギザした痕が付いているもの。よく胖大舌(大きくて腫れぼったい舌)にともなって現れる。日本漢方では一般に歯痕=水毒の状態とすることが多いが、その原因としては、舌色や舌の苔の状態など総合的にみて、脾虚、陽虚、湿熱などを鑑別する必要がある。
|
|
四肢厥冷(ししけつれい)
|
|
四肢(手足)の冷えがひどく氷のように冷たい。
|
|
四診(ししん)
|
|
東洋医学独特の4つの診察方法。望診・聞診・問診・切診。
|
|
膩苔(じたい)
|
|
舌の苔がかなり厚く、べったりと張り付いている状態。こそいでも取れない。湿、痰、食積などを示す。
|
|
七情(しちじょう)
|
|
内邪のうち、生体機能に影響を及ぼすことがある7つの感情。「喜・怒・憂・思・悲・恐・驚」。強すぎる感情は五臓の失調としてあらわれる。喜→心、怒→肝、憂・悲→肺、思→脾、恐・驚→腎。
|
|
湿(しつ)
|
①六気(風・寒・暑・湿・燥・火)の一つ。ムシムシした気候。雨天や梅雨などの自然現象、あるいは水を多く扱う職場環境に多い。雨に濡れたり、湿気の多い環境に長く滞在したときに、体が対応できなければ湿邪となる。外湿。
②脾の機能が低下しているときに水飲が処理できず停留し、湿が発生する。さらに湿の粘稠度が増すと痰飲となる。内湿。
|
|
実(じつ)
|
|
十分にある。多い。余力がある。足りている。満たされている。⇔虚(きょ)
|
|
実寒(じつかん)
|
|
寒証のうち、外からの寒邪の侵入によって生じる症候。⇔虚寒
|
|
衄血(じっけつ/じくけつ)
|
|
鼻血。鼻出血。
|
|
湿困脾胃(しつこんひい)
|
|
寒湿困脾。湿邪によって脾胃の運化機能が障害されたもの。代表方剤は胃苓湯。
|
|
湿邪(しつじゃ)
|
①外邪の一つで、ジメジメした湿気(季節や環境)が生体に影響を及ぼすもの。脾、肺、腎のはたらきを障害し、体が重だるい、関節が痛い、冷たい、むくみやすい、軟便、治癒しにくい等の症状がでる。特に脾虚があると湿邪を感受しやすい。
②体に生じた病理的な水分。
|
|
実証(じっしょう)
|
①体の抵抗力(正気)が充実していて、病邪に対して強い反応を示す状態。原則として「攻法」や「瀉法」で治療する。
②ただし、正気が衰えていて状態的に虚証でも、気血水の流れが停滞し、体内に、湿・痰飲・瘀血などの病理的産物によって、局所的な実証が生じることもある。
③日本漢方では概して、体力がある、体格がよい、顔色がよい、声が大きい、胃腸が強い、暑がり等のタイプ。
|
|
湿痰(しつたん)
|
①≒飲。脾の機能の低下で、胃内の水飲が粘稠度を増し、水飲→湿→湿痰(飲)→痰と変化していく過程の、飲とほぼ同意語。狭義の湿痰。
②体の水液代謝の異常によって生じる病理的な産物(湿・痰飲など)の総称。広義の湿痰。代表方剤は二陳湯。
③肺の痰証で、その性質により湿痰・寒痰・熱痰・燥痰に分類されるうちの一つ。咳嗽、白色で多量の痰、喀出しやすい、胸苦しい、四肢がだるいなど。
|
|
湿熱(しつねつ)
|
|
湿邪に熱邪を伴うもの。炎症があり、浸出液が多い、排泄物・分泌物が黄色い、濁る、臭いが強い、舌苔が厚くて黄色いなどの症状がみられる。治療原則は清熱化湿で、代表方剤は竜胆瀉肝湯。だが、湿邪が重いか熱邪が重いかの違いはあるので、治療も清熱を主とするか化湿を主とするかが変わってくる。⇔寒湿
|
|
実熱(じつねつ)
|
①熱邪の発生(侵襲)によって生じる実証の熱。⇔虚熱(参照⇒実熱と虚熱)
②体内のエネルギーが過剰な状態。神経が高ぶり興奮した状態。
|
|
湿痺(しっぴ)
|
|
⇒着痺
|
|
邪(じゃ)
|
|
体の生命活動を妨げる要因。邪気。⇔正気。体の外から影響を受ける外邪と、体の内側から発生する内邪がある。
|
|
雀目(じゃくもく)
|
症。夜盲症。鳥目。
|
|
瀉下(しゃげ)
|
法。下法。攻下法。内臓(消化器)にある病邪を大便とともに排泄させること。たんに便秘を改善することではない。裏実証に対する治療法の一つ。長期に使用すると正気を消耗するおそれがある。参照⇒瀉下薬とは
|
|
邪正闘争(じゃせいとうそう)
|
|
正気と邪気の戦い。正気(体の病気に抵抗する力)にスキがあると、邪気が侵入してきて、闘いが始まる。正気が強ければ邪気に対する反応も激しい。感冒の初期の発熱はその代表例。
|
|
瀉法(しゃほう)
|
|
実証に対する、過剰なもの・不要なものを取り去る治療。気血水の流れをスムーズにして体内の病理産物を取り除く。それに用いる薬を瀉剤と言う。⇔補法
|
|
炙法(しゃほう)
|
|
生薬を(酒や酢などに浸してから)炒める。酒炙、醋炙、蜜炙(ハチミツと炒める)など。
|
|
渋(じゅう)
|
①脈が渋。渋脈。脈の流れがなめらかでないもの。血虚や血瘀が考えられる。
②渋味。しぶい味。蓮肉、山茱萸などに含まれる味。収斂・固渋の作用をもつ。生薬の「五味」においては酸味が渋を兼ねていて、渋としてはあまり区別されない。関連記事⇒収渋薬
|
|
柔肝(じゅうかん)
|
|
血を養う作用によって肝を柔らげ、肝気がのびやかでないのを緩和する。例⇒芍薬(白芍)
|
|
修治(しゅうち/しゅち/しゅうじ)
|
①生薬を採集してから実際に臨床で用いられるまでに行われる調整や加工。薬用部位を選別したり大きさを整えたりする。炮製の段階のもっとも簡単な方法(準備段階)。修製。生薬によってはこの段階で臨床に用いることができる。
②≒炮製。治療に適するように加熱などの処理をして生薬を加工すること。薬効の増強、もしくは毒性や副作用の軽減、または成分の変換、風味の改良など。
|
|
渋腸(じゅうちょう)
|
|
渋腸止瀉。収渋薬を用いて下痢を止める。
|
|
重鎮安神薬(じゅうちんあんじんやく)
|
|
神経の高ぶりを鎮静させる生薬で、主に鉱物や化石などの、重量が重くて寒涼性のもの。竜骨など。参照⇒安神薬とは
|
|
粛降(しゅくこう)
|
|
肺の機能の一つ。ものを納めて降ろす作用。(1)自然界の清気を吸い込む(2)かつフィルターとしての機能(3)清気や津液、精微(栄養分)を体の下の方に運ぶ、といった役目をもつ。参照⇒宣発と粛降について
|
|
受納(じゅのう)
|
|
胃の機能の一つ。食べ物を受け入れ納めること。飲食物を消化するための第一歩。胃の受納の機能が弱ければ食欲不振がみられることになる。
|
|
潤下(じゅんげ)
|
|
潤腸通便。油脂を含んだ生薬で、大便が硬く乾燥している便秘(腸燥便秘)を解消する。参照⇒潤下薬
|
|
暑(しょ)
|
|
暑い、という自然現象。六気(風・寒・暑・湿・燥・火)の気候のひとつ。夏に多い。暑すぎると暑邪となる。
|
|
証(しょう)
|
①病気の症状。病症。症候。(例:頭痛、下痢、腰痛、…。)
②四診によって得られた情報をもとに分析された病態。(例:寒証、血虚証、脾虚証、…。)
③漢方的診断の結果、この患者にはこの治療法で治るという証(確証)があるものの診断名。(例:葛根湯証、小柴胡湯の証、…。)
|
|
少陰病(しょういんびょう)
|
|
六経弁証(六病位)で、体の抵抗力がかなり衰弱していて、元気がない・寒がる・横になりたがる・いつも眠い、などの症状がみられる段階。病態としては心腎陽虚。代表方剤は四逆湯。
|
|
消渇(しょうかつ)
|
①はげしい口渇。
②のどの渇き(口渇)を感じ、多量に水分を摂る、口渇・多飲・多尿の症状。現代医学的には糖尿病(高血糖)の症状に相当。
|
|
傷寒(しょうかん)
|
①風寒の邪によって引き起こされる疾患。cold damage。⇔温病
②太陽病(頭~項の痛み、悪寒、発熱、脈が浮)の症状があり、とくに悪寒がつよく無汗、身体痛、嘔気があって、脈が緊であるもの。インフルエンザのときのような症状。⇔中風(参照⇒『傷寒論』第3条)
|
|
傷寒論(しょうかんろん)
|
|
張仲景という人物によって書かれた(と伝わる)『傷寒雑病論』が、後世になって『傷寒論』(急性病)と『金匱要略』(慢性病)に分かれる。外感熱病である傷寒(感染症などの急性の発熱性疾患)による病態の推移を、太陽病・少陽病・陽明病・太陰病・少陽病・厥陰病に分けて論じ、診断方法とそれに対する治療原則が記されており、いわゆる六経弁証による弁証論治が確立された。オリジナルは残っていない。印刷技術が発達した宋の時代以前、手書きにより写本されていたものは誤りが多く、各時代ごとに研究者によって再編集が繰り返され、様々なかたちの『傷寒論』が伝わっている。現代でもテキストによって解釈が異なっていることはよくある。
|
|
上逆(じょうぎゃく)
|
|
機能的に下降すべきものが上に昇ること。胃気上逆など。
|
|
情志(じょうし)
|
|
感情。肝の疏泄により調節されている。
|
|
上衝(じょうしょう)
|
|
気が上に昇ること、昇りがちなこと。
|
|
上焦(じょうしょう)
|
|
三焦の上部。三焦が水液の通路であるという意味では、水分が肺の宣発と粛降、心の推動によって全身に散布されていく場所。身体の部位をあらわすときは横隔膜より上部。(胸部・頭部および心・肺をさすこともある。)
|
|
傷津(しょうしん)
|
|
津液の損傷。熱邪(熱性病)での高熱・発汗・炎症、あるいは下痢・嘔吐、その他慢性病などによって、津液が消耗し脱水傾向になる。気の消耗を伴うことがある。
|
|
昇清(しょうせい)
|
脾の機能の一つ。飲食物から清(栄養分)を吸収し、それを小腸から上の方へ運び上げ(上昇させ)、全身を養う。「脾は を主る」
|
|
小腹(しょうふく)
|
|
下腹部の中央。
|
|
少腹(しょうふく)
|
|
下腹部の左右両側。小腹の外側。小腹と区別されず書かれることも多い。
|
|
小腹拘急(しょうふくこうきゅう)
|
|
腹診で、下腹部の腹直筋だけが緊張しているもの。腎陽虚で現れることがある。参照⇒『金匱要略』における八味丸(桂枝加竜骨牡蛎湯証では「小腹弦急」)。
|
|
少腹急結(しょうふくきゅうけつ)
|
|
腹診で、とくに左の下腹部を押すと強い痛みがあるもの。瘀血がある婦人科疾患でみられる。桃核承気湯の腹証。(右側だと大黄牡丹皮湯の腹証とされる。)
|
|
小腹不仁(しょうふくふじん)
|
|
腹診で、下腹部の腹力が(上腹部より)軟弱、あるいは下腹部の知覚鈍麻がある。腎陽虚や腎陰陽両虚を示唆する腹証。代表方剤は八味地黄丸。
|
|
小便自利(しょうべんじり)
|
|
尿量が多い。排尿がコントロールしにくい。尿もれすることがある。
|
|
小便不利(しょうべんふり)
|
|
尿量が少ない。小便が排出しにくい、排出されない。
|
|
小腸(しょうちょう)
|
|
六腑の一つ。胃が受納し腐熟した飲食物を受け取り、さらに消化しながら清濁を選別し、精微物質(栄養分)は脾に、残渣は大腸に送る。心と表裏の関係にある。
|
|
消導薬(しょうどうやく)
|
|
消化を促進する、食欲を増進する、胃腸のはたらきを調整するなどの作用をもち、主に食積内停証に用いられる薬。山査子、麦芽、神麹など。参照⇒消導薬
|
|
消法(しょうほう)
|
|
食滞、血瘀・痰飲・水腫などの病理産物あるいは腫瘤などを取り除く治療。消散法。
|
|
生薬(しょうやく)
|
|
植物・動物・鉱物など天然のもので、薬としての作用をもつ部分のこと。例えば葛根(カッコン)は葛(クズ)という植物の「根」の部分が生薬。葛粉(くずこ)は食品であるが、生薬として葛根を扱うなら薬。医薬品の規格基準書である『日本薬局方』に、その性状や品質について細かく規定されている。
|
|
少陽頭痛(しょうようずつう)
|
|
両こめかみの頭痛。
|
|
少陽病(しょうようびょう)
|
|
太陽病(表証)と陽明病(裏証)の中間的(半表半裏)な病症。胸脇苦満、往来寒熱、食欲不振、口が苦い、吐き気などの症状が特徴。治療は和解法で、代表方剤は小柴胡湯。
|
|
食少(しょくしょう)
|
|
食欲不振。
|
|
食滞(しょくたい)
|
|
消化不良によって飲食物が停滞し、腹部膨満、腹痛、食欲不振、腐臭ある曖気(げっぷ)、呑酸、吐き気、下痢または便秘などを呈する。食積。治療には、程度に応じて消導薬、理気薬、健脾薬、瀉下薬などが用いられる。
|
|
暑邪(しょじゃ)
|
|
外邪の一つで、夏の暑さによって疾病を引き起こす。体が熱くなったりするだけでなく、大量の発汗によって気や津液の消耗(気陰両虚)をきたすので、治療には補気や滋陰の配慮が必要になる。熱射病に相当する「暑熱」の他に、湿邪が結びついた「暑湿」がある(消化器症状を伴う夏風邪など)。
|
|
女子胞(じょしほう)
|
|
子宮。胞宮。奇恒の腑(きこうのふ)に含まれる。
|
|
心(しん)
|
|
五臓の一つ。五行の火に属する。主な生理機能として、神志(精神意識や思考)と血脈(心臓のポンプ機能)をつかさどる。その華は面(顔)にあり、舌に開竅する。(顔の色艶や舌質の状態から血液循環の状態を推測できるし、顔色をうかがってココロの状態を読むこともできる。)
|
|
神(しん)
|
|
精神や意識、思惟活動。「心は神を蔵す」という。はたらきとしては大脳が行うことだが、心が血脈をつかさどり、血が脳を養うので、神志活動が維持されている。神を失うと失神する。(広義では、人の生命活動そのものを指すこともある)
|
|
辛(しん)
|
|
辛味。五味の一つ。生姜・細辛・附子・川芎などの生薬の味。①気血をめぐらせる②発散させる③温める、などの作用をもつもの。五臓では肺にはたらきやすい。⇒生薬の五味について
|
|
津(しん)
|
|
体液で、水のようなサラッとしたものを「津」、濃厚なものを「液」と区別できる。一般的には合わせて「津液」と言うことが多いが、病理変化のとき、例えば津液不足(脱水症状)のときは「傷津」と「脱液」に区別されることがある。
|
|
腎(じん)
|
|
五臓の一つ。五行の水に属する。主な生理機能として、腎は精を蔵し、水をつかさどり、気を納める。(参照⇒「腎」の3つのはたらき)その華は髪にあり、二陰に開竅する。精が貯蔵されているので、腎は成長・発育・老化・生殖をつかさどる場所とされる。
|
|
腎陰(じんいん)
|
①腎精と同じ意味。生命活動の基本的物質。元陰。真陰。
②身体、各臓腑の、陰(潤い)の源。腎水。
腎陰虚では、腎虚の症状とともに、虚熱の症状があらわれやすい。
|
|
津液(しんえき)
|
|
体内の正常な状態の水液。血(けつ)以外のあらゆる透明な液体。細胞の内外にある液から、汗、唾液、胃液なども津液に入る。日本漢方でいう「気・血・水」の水(すい)。水のようにサラッとしたものを「津」、ネットリなものを「液」と分けることもできる。いずれにしてもH2Oだけじゃなく、そこに溶け込んでいる成分もすべて含める。
|
|
辛温解表(しんおんげひょう)
|
|
辛温の性味をもつ解表薬を用いて、体表の風寒邪を発散させる。参照⇒辛温解表薬
|
|
心火(しんか)
|
|
心の陽気(機能)の過亢進。憂鬱な精神状態によって起こることがある。心火が燃え上がると神を乱すので、いらいらして落ち着きがなくなる。不眠、多夢、口内炎などがみられる。心火上炎。心火旺。黄連が心火を抑える(瀉する)作用に優れていて瀉火薬としてよく配合される。
|
|
心下(しんか)
|
|
みぞおちの周辺。心窩部。
|
|
心下悸(しんかき)
|
|
腹診で、心下(心窩部)に感知される動悸(腹部大動脈の拍動)。
|
|
心下痞(しんかひ)
|
|
心窩部(みぞおち)がつかえる感じはするが、押しても軟らかいか痛まないもの。
|
|
心下痞硬(しんかひこう)
|
|
心窩部(みぞおち)がつかえる感じがするだけでなく、押すと硬い抵抗や圧痛があるもの。
|
|
真寒仮熱(しんかんかねつ)
|
|
ほてりやのぼせ、口渇等(見かけの熱証)を訴えてはいるが、実際には体の芯や四肢が冷えている、消化不良性の下痢をする、温かいものを好むなど寒症状を有する病態。内臓の寒が強すぎて熱が外部に浮いてくる現象と考えられる。このときは温熱薬を用いるべきである。⇔真熱仮寒
|
|
心悸(しんき)
|
|
胸がドキドキすること。動悸。不整脈。内因性のもの(→怔忡)と外因性のもの(→驚悸)がある。
|
|
腎気(じんき)
|
①腎精をもとに行われる腎の生命活動。腎陽とも言う。
②腎臓自身の機能。
|
|
腎気不固(じんきふこ)
|
|
腎気虚。腎虚の症状とともに、頻尿・尿もれ・残尿・夜尿などの泌尿器系の症状や、夢精・性欲減退などの生殖器系の症状がみられる。腎気の衰えにより、体内から簡単には体外に排出しないようにされているものが、漏れてしまう状態。
|
|
腎虚(じんきょ)
|
①腎精の不足。泌尿生殖器系、ホルモン系、栄養代謝系、自律神経系などの機能の減退による症状。老化。
②腎陰虚や腎陽虚など腎の虚証を総称したもの。
|
|
心身一如(しんしんいちにょ)
|
|
「こころ」と「からだ」は密接に関わり合っているので、切り離して考えることはできない、という東洋医学の考え方。病は気から。
|
|
振水音(しんすいおん)
|
|
胃腸の水分代謝が悪いときに、胃のあたりを軽くたたいたり揺すったりすると鳴るポチャポチャという音。関連用語:胃内停水
|
|
腎精(じんせい)
|
腎に貯蔵されている精。生命活動の基本的物質。生命力の基礎。全身の陰陽の元。ホルモン。
腎精は、骨・歯・髄・脳・生殖の精などを作る原料でもあるので、腎精が不足すると、骨格・知能・目や耳のはたらき・生殖機能などが衰え始める。「私の人生は、 次第なのか…」
|
|
身熱(しんねつ)
|
|
身体のほてり。
|
|
神農(しんのう)
|
|
人々に農業と胃薬を教え、くすりの神様としても信仰される古代中国の伝説上の帝王。別名:炎帝。薬草は自らなめて鑑定し、その有効性と安全性を人々に教えたと言い伝えられている。
|
|
神農本草経(しんのうほんぞうきょう)
|
|
生薬について書かれた中国最古の書物。生薬を上品・中品・下品に分類している。関連記事⇒『神農本草経』における生薬のランク分け
|
|
心煩(しんはん)
|
|
胸中の煩悶。不安やイライラで、胸苦しい。
|
|
心包(しんぽう)
|
|
心臓を包む膜。心包絡。心を保護する作用がある。古典では、邪気が心臓を侵すとき、直接心が邪を受けるのではなく、まず心包が最初に影響を受けるとされている。「熱入心包」などと表現される。経絡的には三焦と表裏の関係にある。
|
|
腎不納気(じんふのうき)
|
|
腎の「納気をつかさどる」機能の低下。吸気性の呼吸困難。
|
|
腎陽(じんよう)
|
①「腎気」の温煦作用を強調した言い方。
②身体の熱源。各臓腑の機能を促進し、温煦する作用。命門の火。元陽。真陽。
腎陽虚では、腎臓自体の機能低下とともに、体全体の機能の低下や、冷えの症状(寒証)があらわれる。
|
|
辛涼解表(しんりょうげひょう)
|
|
主に辛涼の性味をもつ解表薬を用いて、風熱の邪を発散(疏散)させる。参照⇒辛涼解表薬
|