9.消導薬(しょうどうやく)
消導薬とは、主に食積内停証に用いられる薬です。
消導(消化を促進する)、開胃(食欲を増進する)、和中(中焦の胃腸のはたらきを調整する)などの作用をもちます。
「食べすぎ」て、消化されない飲食の積滞によって起こる、腹満、腹痛、悪心、嘔吐、食欲減退、曖気(げっぷ)、呑酸、通便異常など。
暴飲暴食による宿食は、邪気と同様に、胃腸の気機(気の動き)を妨げ、このような症状が起こります。
もともと脾虚(胃腸虚弱)の場合は、通常の飲食であっても食後の膨満や消化不良などは起こり得ますが、このときは健脾薬を主に用いるべきですし、
その他、気滞、湿熱、裏寒などを伴うときにも、消導薬だけではなく、それぞれに適した薬の配合も必要になります。
また、常に食べ過ぎの傾向あって糖尿病や高脂血症などであれば、そちらの治療とともに生活習慣の改善も大切です。
一方で、現代の食習慣の変化におきましては、
噛む回数の減少、冷たいものの常飲食、不規則な食事時間などの影響で、必ずしも食べすぎているわけでないのに、消化不良を起こしやすくなっています。
逆流性食道炎などでよく処方される胃酸分泌抑制薬の長期服用でも消化力は落ちてきます。
高齢者のフレイル予防の面でも、食べ物がしっかり消化され、栄養を吸収できているかどうかも重要です。
よって、消導薬を使用する機会はまだ増えるかもしれません。
山査子/山楂子(さんざし)

バラ科オオミサンザシ、野山楂などの成熟果実(偽果)
※漢方で用いる他、ドライフルーツやジュース、果実酒としても利用されます
※セイヨウサンザシは代用になりません
【帰経】脾 胃 肝
【効能】消食化積 活血散瘀
酸味があります。
消化に関しては、特に肉料理(脂っこいもの)の食積に適しています。
その他、胃腸虚弱、食欲不振、消化不良、腹痛、(暴飲暴食による)下痢などに用いられます。
胃酸の分泌を促す作用があるとされ、胃酸の分泌の少ない人にも使用できます。
例⇒加味平胃散、啓脾湯、化食養脾湯、保和丸
単味で食べても胃がスッキリします。
その他、活血散瘀のはたらきがあり、月経痛や、産後の腹痛・悪露の停滞に使用されることがあります。
現代ではこの血行改善作用は高脂血症、高血圧、動脈硬化症などに適すると考えられます。
神曲/神麹(しんきょく,しんぎく,しんきく)

加工品:麩(ふすま)を含む小麦粉に、鮮青蒿・鮮辣蓼・鮮蒼耳の液汁と杏仁・赤小豆の粉末を混合して発酵させたもので、酵母やビタミン類が含まれる。6種類の植物から作るので六麹・六神曲などともいう。
日本では米麴で代用されることがあります。
【帰経】脾 胃
【効能】消食和胃
胃もたれや消化不良、食欲不振、下痢に用いられます。
ビール酵母で作られているエビオス錠(Asahi)なども効能の理論は同じだろうと思われます。
漢方薬では、半夏白朮天麻湯、加味平胃散などに配合されます。
麦芽(ばくが)

イネ科オオムギの種子を発芽させたもの
【帰経】脾 胃 肝
【効能】消食和中 回乳
デンプン(炭水化物)を糖に分解する酵素(アミラーゼ)が含まれています。
ですので消化の面では、特に米・麺・芋などの炭水化物の積滞に適しています。
漢方薬では、半夏白朮天麻湯、化食養脾湯などに配合されます。
また炒麦芽は、古くから断乳(離乳時に乳汁分泌を止めるとき)や乳汁のうっ滞による乳房の脹痛、母乳の出過ぎるのを抑える際に用いられてきています。そして近年になっては高プロラクチン血症に応用されることがあります。
萊菔子(らいふくし)
アブラナ科ダイコンの成熟種子
【帰経】脾 胃 肺
【効能】消食化積 降気化痰
食積を消すだけでなく、気を降ろすこともできるので、
食積による中焦の気滞証で起こった、腹満、痞え、曖気(げっぷ)、呑酸、腹痛などの症状に、
山査子や神曲、陳皮などと配合して用いられます。⇒保和丸
その他、痰の多い咳嗽、呼吸困難にも良いとされています。
鶏内金(けいないきん)
キジ科ニワトリの胃の一部である砂嚢(砂ぎも、砂ずり)の内膜
【帰経】脾 胃 小腸 膀胱
【効能】運脾消食 固精止遺
食積の腹満、消化不良、または脾虚の食欲不振などに用いられます。
遺尿、頻尿、遺精の軽いものに使われます。
その他、結石を消す効能があるとされ、胆石や尿路結石などに金銭草とともに用いられていたようです。

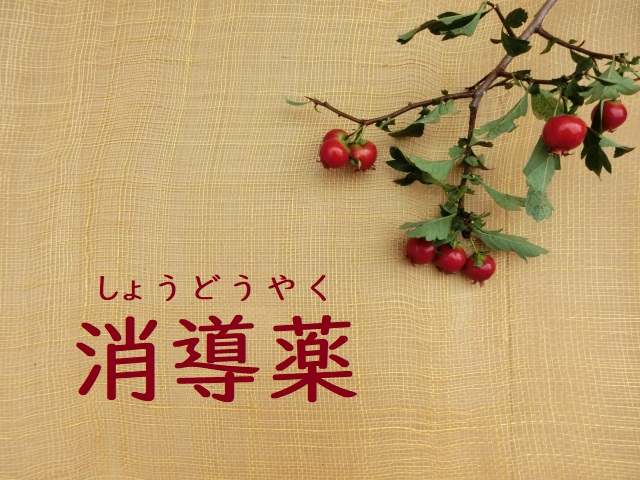


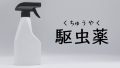
コメント