桃核承気湯(とうかくじょうきとう)の解説
桃核承気湯は、別称「桃仁承気湯」とも言います。
「○○承気湯」と名の付くグループのひとつであり、
このグループは基本的に便秘をともなう症状に使います。
下腹部の血の流れをよくする桃仁(桃核)が配合されることから、瘀血または月経に関連した症状に幅広く使われています。
構成生薬について
配合される生薬
※大黄・甘草の2つで「大黄甘草湯」です。
※大黄・甘草・芒硝の3つで「調胃承気湯」です。
○○承気湯のグループに共通する、大黄と芒硝の組み合わせが含まれます。
また、現在は桂皮が使われていますが、原典では桂枝(ケイシ)ですので、以下の解説は桂枝で書きます。※桂枝と桂皮の違いについてはこちら
瘀血に対する配合の特徴
生薬構成は、大黄・芒硝・甘草からなる「調胃承気湯」に、桃仁と桂枝を加えたものに相当します。
つまり
+
「血を巡らせる桃仁」
+
「気を巡らせる桂枝」
という構成です。
方剤の名前に「桃仁」(=桃核)が入るくらいなので、桃仁が主薬であり、血を巡らせる薬「駆瘀血剤」に分類されます。
「気」は血液の流れを推進するものですので、病理的に、もし「気」の異常があれば、血行不良を引き起こし、血瘀にいたる可能性があります。
よって、瘀血の治療の際には、駆瘀血薬(活血薬)のみではなく、しばしば「気」を巡らせる薬が一緒に配合されます。
それが桃核承気湯においては「桃仁+桂枝」です。
この「桃仁+桂枝」のペアは、桂枝茯苓丸や、折衝飲にもみられます。
調胃承気湯の瀉下作用というのは、言わば、腹部につっかえているものを下に流すことなので、瀉下することで気血が流れやすい状況を作り出します。(⇒瀉下薬とは)
また「桃仁」には油脂が含まれ、通便を良くする作用もあるので、調胃承気湯の瀉下作用を強化しますし、
逆に、調胃承気湯に含まれる「大黄」には、駆瘀血作用があります。
つまり「桃仁」と「調胃承気湯」と「桂枝」という組み合わせは、すべて駆瘀血(血をめぐらせる)作用への相乗効果をねらった配合だと考えることができます。
効能・適応症状
というわけで、桃核承気湯は、瘀血に対する生薬構成ですので、
駆瘀血剤としてさまざまな症状に幅広く応用することができます。
例えば↓のようなものに使用されることがあります。
- 月経痛、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、こしけ
- 月経時や産後の精神不安
- のぼせ、イライラ、興奮、ヒステリー、不眠などの精神神経症状
- 常習便秘
- 腰痛、坐骨神経痛、リウマチ、打撲や捻挫によるうっ血(内出血)、痔
- 高血圧に伴う頭痛・めまい・肩こり、動脈硬化
- 湿疹・蕁麻疹などの皮膚疾患、にきび、しみ、強い痒み
- 月経異常を伴う吐血・下血・鼻血
添付文書上での効能・効果
【ツムラ・クラシエ他】
比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症:
月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)
【コタロー】
頭痛またはのぼせる傾向があり、左下腹部に圧痛や宿便を認め、下肢や腰が冷えて尿量減少するもの。常習便秘、高血圧、動脈硬化、腰痛、痔核、月経不順による諸種の障害、更年期障害、にきび、しみ、湿疹、こしけ、坐骨神経痛。
【薬局製剤】
体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症:
月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)、痔疾、打撲症
駆瘀血剤として、月経に関連したもの以外にも適応が付いています。
しかし、製品によって適応症が異なりますので気をつけてください。
コタローの添付文書にある「尿量減少するもの」という部分はあまりこだわらなくていいかなと思います。
最近では大腸手術の予定の方に術前の薬として使用されることもあるようです。
また、抗うつ薬を服用中の、副作用による便秘の改善に(精神安定の効果もかねて)桃核承気湯との併用も考えられます。
桃核承気湯のポイント

桃核承気湯は、便秘に用いる調胃承気湯(大黄・甘草・芒硝)がベースに入っている漢方薬ですので、基本的には、便秘傾向の人に適しています。
血瘀の状態が(桂枝茯苓丸を用いる状態よりも)ひどいことが多く、
月経痛に関しては、月経がはじまる前から痛みが起こり、痛みが強いタイプの人、
また、血瘀によって気の巡りもわるく、ヒステリーを起こしかねないくらい激しくイライラしてしまう人に用いられます。
瘀血によって便秘になっている、または、便秘によって瘀血になっていることも考えられますが、一般的に、瘀血の程度がひどい人は便秘をともなうことが多く、そのような人にはよい適応となります。
月経と関連した症状に使われることが多いですが、男性が使われても問題ありません。
便秘をしていてさらに瘀血の程度が強いときや、気うつ・気滞をともなうときは、通導散も使われます。
月経に関連した症状に用いる理由

女性においては月経に関連した症状に用いられる理由をもう少し補足します。
月経時には、下腹部に「血」が集まってきますので、下腹部に熱がこもった状態では、水分が消耗した状態のように、粘稠度が高くなり、血の流れがわるくなります。
そして、下腹部(骨盤内)で血行不良が生じていることによって、下肢や腰部は冷えやすくなりますが、頭部の方は逆に行き場をなくした熱が昇ってきて、のぼせ(冷えのぼせ)がみられたり、イライラなどの精神症状が起こりやすくなります。
それに月経痛・腰痛・頭痛・肩こりを伴うことがあります。
「桃核承気湯」には下腹部の血流を改善する大黄・桃仁、(大黄には清熱作用もありますし、)気の流れを改善する桂枝が配合されていますので、月経に関連して起こる、冷えのぼせやイライラに適したものになってきます。
ただし、桃核承気湯を使う場合は、やはりまず、便秘を伴った症状である、または腸や下腹部に熱がこもった状態である、ということが前提です。
副作用・注意点
桃核承気湯の単独では、気血を補う効果はあまり期待できません。体力の低下している人、虚弱な人、下痢しやすい人には使えません。
そうでなかったとしても大黄が配合されていますので、漫然とした長期服用は避けるべきです。
服用中に下痢をした場合は中止してください。また、便秘をしていないときは、桂枝茯苓丸や加味逍遥散など他の方剤に変えることを検討してください。
妊娠中の方は、桃仁などの妊娠中は慎重に用いることとされている生薬が配合されているため、あらかじめ主治医にご相談ください。(禁忌ではありません)
長期に服用するときは、甘草による副作用の発現に注意が必要です。
桂枝茯苓丸・大黄牡丹皮湯との使い分け
| 大黄 | 芒硝 | 甘草 | 桃仁 | 桂枝 | 茯苓 | 牡丹皮 | 芍薬 | 冬瓜子 | |
| 桃核承気湯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 桂枝茯苓丸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大黄牡丹皮湯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
駆瘀血剤として代表的な3処方です。
大黄・芒硝の組み合わせは「大黄牡丹皮湯」にもみられますし、桃仁・桂枝の組み合わせは「桂枝茯苓丸」にもみられます。
が、逆の見方をすれば
「桂枝茯苓丸」には大黄・芒硝が入らないので、「便秘」があれば桃核承気湯の方が適する。
「大黄牡丹皮湯」には桂枝が入らないので、「のぼせ」「イライラ」があれば桃核承気湯の方が適する。
ということになります。
桃核承気湯の出典
『傷寒論』(3世紀)より
太陽病解さず、熱膀胱に結び、その人狂の如く、血自ずから下る、下る者は癒ゆ。その外解さざる者は、尚未だ攻むべからず、当に先ず其の外を解すべし。外解し已りて、但だ少腹急結する者は、乃ち之を攻むべし、桃核承気湯が宜し。」
→(訳)太陽病が治癒しないとき、(邪が太陽経の膀胱に達して)下焦に熱が集まって、ある人は精神症状が現れます。このとき瘀血が大便とともに排出されれば自然と治ります。瘀血が残っていれば、攻めた治療をしなければいけないが、太陽病の表証が残っているならまだ攻めてはいけない。まず表証を解消するべきです。表証が治っているのに少腹急結(※)の症状があるならば、すなわちこれは攻めるべきです。桃核承気湯が良いでしょう。
※下腹部の圧痛が過敏である症状で、これがいわゆる桃核承気湯の腹証と言われるものです。

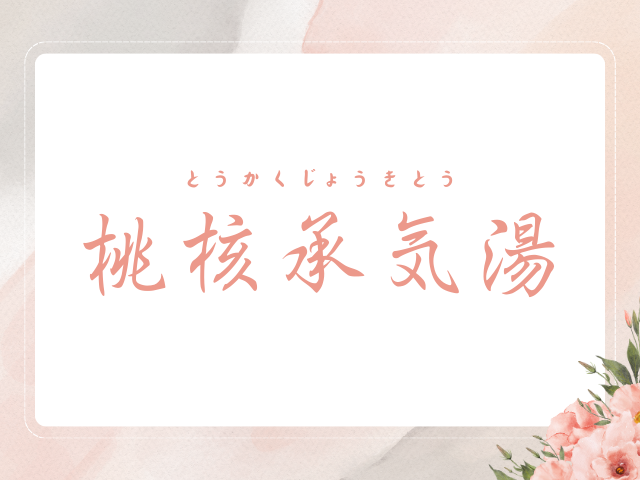



コメント