桂枝と桂皮は同じ植物。使用する部位が異なります。
桂枝(けいし)と桂皮(けいひ)は、いずれもクスノキ科の常緑高木で、基原植物は同じです。
生薬としての肉桂(にっけい)と呼ばれているのは「桂皮」とほぼ同じです。(肉桂は中国由来の言葉)
シナモンスティックと同じで良い香りがします。
通常、植物の部位が異なれば、含まれる成分も効能も違ってくると考えますので、中医学においてははっきり区別しています。
薬を効能別に分類した教科書では、それぞれ載っている項目からして違っていて、全く別の薬であるかのような扱いです。
しかし、日本の局方(日本薬局方)には「ケイヒ」(肉桂)の規定しかありません。
エキス製剤ではメーカーにもよりますが「桂枝」と「桂皮」の使い分けがあいまいなところがあります。
よって桂枝湯なのに桂皮を使っているの? という疑問には必ず遭遇してしまいます。
なお、漢方薬で使われる桂皮と、香辛料で使われるシナモン(セイロンケイヒ)は 同じ仲間(クスノキ科ニッケイ属)ですが、種(しゅ)としては違うものです。 (「ニッケイ」の根皮のことを指して「ニッケイ」といわれるもの「ニッキ」といわれるものも、漢方用のものとは種や使用部位が異なるはずです。) 香りは似ていても成分の組成は異なると考えられますので、安易に転用はしないでください。
特に、カタカナで「ニッケイ」とだけ表記されたものは、植物名を指している場合、生薬(薬品)を指している場合、香辛料(食品)の商品名を指している場合など分かりにくいものがありますので、混同されないようにしなければいけません。
※桂皮のことをなぜ肉桂と呼ぶのか、いくつかの理由がみつかりましたが、定かではありません。
・「肉」は、幹の皮が薄っぺらいものではなく、肉のように分厚いということを意味している
・「肉」は、表皮などの不要部分を取り去る加工をしているものを指している
・中国の民謡の中の言葉が由来となっている
など

日本薬局方の桂皮(ケイヒ)の刻み
クスノキ科ニッケイ属の「葉」は、先が伸びた楕円型で、太い葉脈が縦方向にくっきり3本だけ走っているのが特徴です。(ベイリーフなど)
クスノキ科ゲッケイジュ属(月桂樹)の葉は、香辛料のローリエとして知られています。よく似ていますが、葉脈は縦に太く1本で、そこから横方向にも多数広がっていますので、区別できます。
桂枝と桂皮の作用
日本の今の漢方薬の場合、
例えば漢方専門薬局で作られる一部の煎じ薬を除いて、
製品として成分名が表記されているもの、医療用やOTC(一般用医薬品)のエキス製剤、薬局製剤などに、実際に使用されているのは、基本的にはほぼ「桂皮(ケイヒ)」です。
でも本来は、桂枝と桂皮は使い分けがありました。
桂枝について
桂皮に比べると作用は穏やかですが、解表作用(体表を温める)をもちます。麻黄や生姜などと同じ分類に入ります。
そのため、発汗作用をメインに使う方剤では「桂枝」が適します。
その他、経脈を温めたり、気血の流れをよくする作用があるため桂枝茯苓丸や温経湯に配合されたり、 利水薬の働きを強めるために五苓散や苓桂朮甘湯などに使われています。
桂皮(肉桂)について
作用が強く、温裏薬として、附子や乾姜などと同じ分類に入ります。
体内から温めたい場合は、「桂皮」(肉桂)を使用した方がいいとされます。 八味地黄丸・十全大補湯・人参養栄湯など。
例えば、桂枝が使われている方剤であっても、冷えが強い場合、桂枝を肉桂に代えてみるのもいいかもしれません。

勉強や調べものをするときの注意点
参考書やネットで漢方薬を調べるとき、 中医学の伝統を汲んでいる書物や、中医学を習得された方の記事は、 おそらく絶対に「桂皮」と「桂枝」は区別して書き分けています。
逆に日本漢方では「桂皮」と「桂枝」を区別しないことも多いです。 そもそも、局方品を使おうと思えば「ケイヒ」しかないわけですから。
ということは、 仮に「桂皮」を使っている、と書かかれているとき、
著者の考え方や立場によっては、「桂枝」でも「桂皮」でも区別なく本当はどちらでもいいよ、という場合や、「桂枝」じゃなくてあえて「桂皮」なんだよという場合、違いなんて分からないけど局方品だから「ケイヒ」なんじゃない? という場合等、様々な状況が推測されます。
より正しく理解するにはその点を意識して読む必要があります。
なぜ、使い分けがあいまいなのか
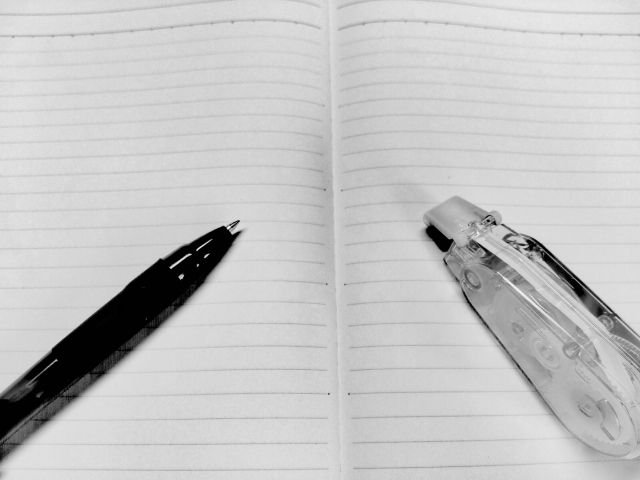
歴史的にはある時期を境にして、(いわゆる流派によって)使い分けが改められていることなどもあるらしいですが、 大きな理由の一つには、 昔の書物というのは、コピー機などありませんから、一文字ずつ書き写す必要があったわけで、その写した人によって、似た文字において写し間違いが生じているとのことです。
「胃」と「骨」などの間違いであれば、文脈から気付けますが、「枝」と「皮」の字体も実はよく似ていて混同が起きている可能性があるということです。
後の人が、間違えていると思って正しいものまで誤修正されたり、オリジナルがどちらか分からない部分もあるようです。

枝か皮か
さらに、3世紀の『傷寒論』などには「桂枝」と書かれていたとして、つまりオリジナルの書物には「桂枝」と書かれていたことが正しかったとして、その場合でも、当時本当に「枝」部分だけしか使っていなかったのか、という疑問も残ります。
しかし、どちらが正解なのか分からなくても、それぞれの効能を把握して、必要に応じて読み分けられるようにしておけば問題ないのではないかと思います。
部位と効能の対応関係

人が立って、上方または左右へ両腕を伸ばしている姿を思い浮かべて頂いて、 その人と同じ大きさの樹木が上方または前後左右に枝葉を伸ばしている様子とを重ねて頂くといいのですが、
そうすると、枝の部分、つまり「桂枝」は、人の上部、頭部、体表部に、
木の幹の部分、つまり「桂皮」は、人の体幹部分に重なります。
「桂枝」の作用も主に、人の上部、頭部、体表部に、 「桂皮」の作用も主に、体の内側に効くことを期待して使いますので、 木の部位と、人への作用点が一致していることになります。
体の作用させたい部位に応じて、使用する部位を変えれば良いというのは古くからある考え方です。 単なるこじつけと考えるかどうかはあなた次第です。



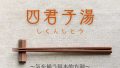
コメント