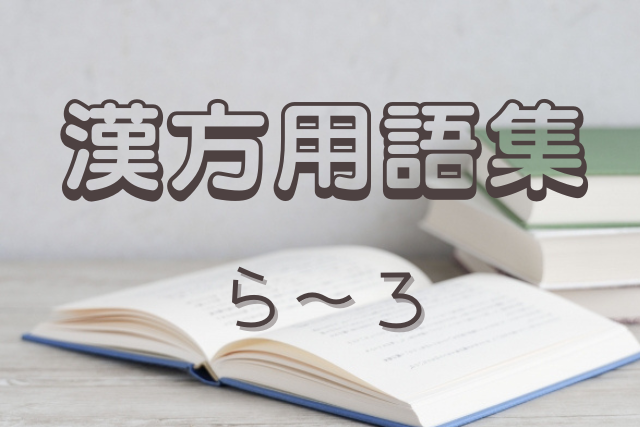“ら行”の漢方用語の説明
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
ら
- 絡脈(らくみゃく)
- 経絡系統の、経脈から横方向に分かれた細い枝で、網目状に巡行し、経脈どうしをつないでいる。
- 懶言(らんげん)
- 話すことも億劫になるほど疲労感があること。気虚の症状のひとつ。
- 闌門(らんもん)
- 小腸と大腸の境。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スポンサーリンク
り
- 裏(り)
- 身体の深部または内臓。↔表(ひょう)。一般に病邪は表から裏へ、しだいに侵入する。
- 理(り)
- 弁証論治において、四診により病気の原因や状態を分析すること。
- 裏寒(りかん)
- 裏が冷えている。それによって下痢をする、お腹が痛くなる、手足が冷える、うすい唾液が口にたまる、脈が沈んで遅くなる、などが起こる。寒邪が直接体に入る「裏実寒」と、陽虚による「虚寒」があるが、両方のことも多い。裏寒証には、人参湯・真武湯・四逆湯などが用いられる。
- 裏急後重(りきゅうこうじゅう)
- 下痢で、頻繁に便意を催す(あるいは残便感がある)のに、便が出ないか少ない。急激な腹痛や、肛門部の灼熱感をともなうこともある。感染性の下痢で起こりやすい。しぶり腹。テネスムス。葛根黄連黄芩湯や、黄芩湯などが用いられる症状。
- 理気(りき)
- ①気を正常に巡らせる。気の運動をスムーズにさせる。主に気滞に対する治療法。行気ともいう。参照⇒理気薬とは
②気滞に対する「行気」、肝気鬱結に対する「疏肝理気」、気逆に対する「降気」、以上をまとめて理気と総称する。 - 理気活血(りきかっけつ)
- 気血の流れを円滑にすること。
- 李時珍(りじちん)
- 明の時代の名医。中国各地の薬草や民間療法の情報を収集し、その集大成として『本草綱目』を著す。
- 痢疾(りしつ)
- 腹痛、裏急後重、膿血便を主症状とする疾患。
- 李朱医学(りしゅいがく)
- 李東垣(りとうえん)と朱丹渓(しゅたんけい)が提唱した医学。その時代名から金元医学とも呼ばれる理論のひとつで、体力を補うことを重視している。これを中国で学んだ田代三喜が日本に広めたことを契機に、陰陽五行・臓腑経絡の考え方は踏襲しつつも、日本独自の漢方医学というものが発展していく。
- 裏証(りしょう)
- ①病邪が体の深部や内臓に侵入し、臓腑の機能に障害が引き起こされていると考えられる状態。裏証にも虚実・寒熱の別がある。
②外感病の表証(ひょうしょう)と半表半裏証(はんぴょうはんりしょう)以外。一般の疾患のほとんどは裏証である。 - 利水(りすい)
- 溜まっている水(水腫、浮腫、消化管内の水など)をさばく(処理する)こと。利水滲湿。参照⇒利水滲湿薬とは
- 六経(りっけい)
- 太陽経、陽明経、少陽経、少陰経、太陰経、厥陰経の6つの経絡。
- 李東垣(りとうえん)
- 中国の金元時代を代表する補土派の医師で、補中益気湯を創ったことでよく知られる。著書に『脾胃論』や『内外傷弁惑論』。(1180-1251)
- 裏熱(りねつ)
- 裏に熱がある。寒邪が化熱する場合と、熱邪が裏に直接入った場合がある。顔面紅潮、悪熱、煩躁、口渇、便秘(もしくは悪臭のある下痢)、尿が濃い、舌苔が黄、などが起こる。裏熱証には白虎湯・承気湯などが用いられる。
- 溜飲(りゅういん)
- ①心窩部につかえがあり、胃酸が上がってくること。胸やけ。胸のつかえ(「
②胃内停水。
③水毒の総称。 - 料(りょう)
- 〇〇料。本来は丸剤や散剤の方剤を、煎剤として用いる場合には、その方剤名の末尾に料の字を付ける。例:桂枝茯苓丸を煎じて作ると「桂枝茯苓丸料」となる。一般に「〇〇散料」とするより本来の「〇〇散」の方が、使用する各生薬の分量が少なくて済む。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スポンサーリンク
る
- 類聚方(るいじゅほう)
- 古方派である吉益東洞の代表作のひとつ。『傷寒論』『金匱要略』の重要な方剤を、それと同じ類の方剤を集めてグループ化し、それぞれの違いを勉強しやすくした画期的な書籍。(1764)
- 類聚方広義(るいじゅほうこうぎ)
- 14代将軍徳川家茂の侍医も務めた尾台榕堂の著書。吉益東洞の『類聚方』の義を広めるという意味で、自身の使用経験も加えられた、評価の高い漢方解説書。(1856)
- 羸痩(るいそう)
- 過度に(病的に)瘦せていること
- 瘰癧(るいれき)
- 頚部リンパ節の腫れ
- 霊枢(れいすう)
- 『素問』とならぶ重要な東洋医学の古典。別名「鍼経」とも呼ばれ、鍼灸を学ぶ者にとってのバイブル。
- 冷服(れいふく)
- 漢方薬を冷ましてから、あるいは冷たくしてから服用すること。漢方薬は温服が基本とされるが、症状によっては冷服が望ましいこともある。出血時、嘔吐時など。
- 裂紋舌(れつもんぜつ)
- 舌面に(深さ・形・数の一定しない)溝や割れ目のあるもの。一般には津液不足や陰虚をあらわす。ただし、先天性のこともあり、その場合は異常所見とはならない。
- 斂汗(れんかん)
- 止汗。固渋法の一つで、自汗や盗汗に対する治療法。参照⇒収渋薬
- 攣急(れんきゅう)
- ひきつけ。急にこわばること。腰や脚が引きつれて痛むことを、腰脚攣急と言う。(足のひきつりが連日続くことを大型攣急、とは言わない。)
- 斂肺(れんぱい)
- 止咳。固渋法の一つで、肺虚による慢性咳嗽に対する治療法。参照⇒収渋薬
- 漏(ろう)
- 血便(漏下)や性器出血(経漏)などの出血で、少量で持続性のもの。大量で一時的なものを「崩」といい、合わせると「崩漏」。
- 労咳(ろうがい)
- 肺結核。結核菌による感染症。
- 弄舌(ろうぜつ)
- 舌をペロペロ出して、口のまわりをなめまわしてしまうこと。口唇の煩熱などが考えらえる。
- 六淫(ろくいん)
- 六邪。自然界の気候の変化[風・寒・暑・湿・燥・火(熱)]のどれかが強すぎたりして、人体に作用し、疾病を発症させる状況になった場合に、これらは風邪・寒邪・暑邪・湿邪・燥邪・火邪(熱邪)という外邪になり、六淫と呼ばれるようになる。
- 六邪(ろくじゃ)
- ⇒六淫(ろくいん)
- 六腑(ろくふ)
- 小腸・大腸・胃・胆・膀胱・三焦。五臓が気血津液を作るための材料、あるいは五臓によって作られた生成物を通過させる、空洞の器官。飲食物の消化吸収と、不要物の排泄に関わる。五臓と六腑は表裏の関係をもつ。関連記事⇒五臓と六腑の違い
- 六気(ろっき)
- 自然の6種類[風・寒・暑・湿・燥・火]の気候変化。六気は自然現象で通常は無害。
- 六経弁証(ろっけいべんしょう/りっけいべんしょう)
- 『傷寒論』における弁証で、外感熱病にみられる病態の推移、主として寒邪による陽気の消耗の経過を、太陽病・少陽病・陽明病・太陰病・少陰病・厥陰病という6つの段階(六病位)に分ける方法。
- 論治(ろんち)
- 弁証に基づいて、どのように治療するか(治療方針・治療原則に従って)具体的な方法を立てること。必ず弁証の結果に基づくという点が、症状に応じて治療する「対症療法」との相違点。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スポンサーリンク
れ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スポンサーリンク
ろ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました