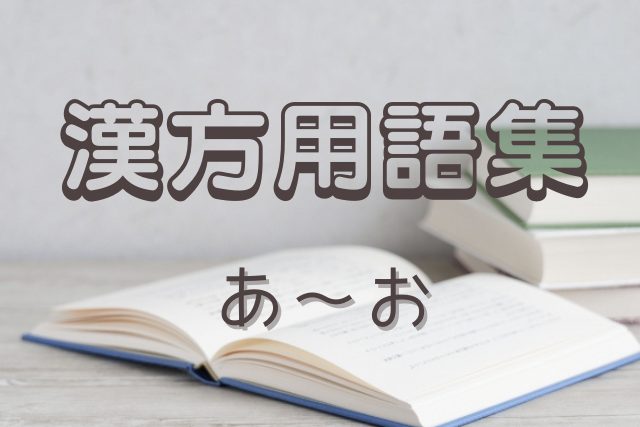“あ行”の漢方用語の説明
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
あ
| 曖気(あいき) |
| おくび。いわゆる「げっぷ」のこと。胃の中のガスが(音とともに)口外に出る。噫(あい)とも言う。 |
| 暗経(あんけい) |
| 無月経 |
| 曖腐(あいふ) |
| (腐敗臭をともなう)げっぷ。 胃の中の臭いが口から出る。 |
| あおそこひ |
| 緑内障。眼圧が高くなって起こり、瞳孔が散大して青い色に見えることから。 |
| 呃逆(あくぎゃく) |
| しゃっくり。吃逆(きつぎゃく)とも言う。 「 |
| 按診(あんしん) |
| 腹部や手足、痛む場所などを、手で触ったり押したりして、かたい・やわらかい、熱い・冷たい、痛み・腫れの有無などを確認し、からだの状態を調べる方法。信頼関係のない状態で行うとセクハラになるので注意すること。按診と脈診は、切診に含まれる。 |
| 安神法(あんじんほう) |
| 不眠、悪夢、胸のドキドキなどの精神不安を治療する方法。 |
| 安神薬(あんじんやく) |
| 精神を安ずる薬、すなわち精神安定や鎮静の効能を有する薬物。重鎮安神薬(じゅうちんあんじんやく)と養心安神薬(ようしんあんじんやく)に分けられる。 |
い
| 胃(い) |
| 六腑のひとつ。西洋医学的な胃と同じもの。飲食物をいったん受け入れて貯留し、初歩的な消化(腐熟)を行い、小腸へ送る。脾とは表裏の関係にある。 |
| 医案/医案書(いあん/いあんしょ) |
| 症例/症例集。病人を診断・治療した際の、病状や診療の記録。医按、治験、病案ともいう。医案を書くことは、自身の自己研鑽のためでもあり、後学者の学びにも役立つ、そのためには正確な医案でなければならない。 |
| 萎黄(いおう) |
| 皮膚が黄色くくすんでいて艶がない。 |
| 畏寒(いかん) |
| 寒さに弱い・寒さが気になる・寒気を嫌がる。悪寒ほどではなくて、温かくしても寒気はするものの緩和されやすい。 |
| 胃脘(いかん) |
| 胃。胃袋。胃を上中下の3つに分けた場合、上脘(噴門を含む)・中脘(胃体部)・下脘(幽門を含む)と言い、それらを合わせた言い方。 |
| 胃脘痛(いかんつう) |
| 胃痛・上腹部痛。 |
| 胃気(いき) |
| 胃の機能。 消化機能。飲食物を受け入れて収納し最初の消化を行う機能。胃気が保たれていれば食欲がある。生きるためにも必要な力。 |
| 胃気上逆(いきじょうぎゃく) |
| 胃は本来、食べ物を下へ向かって運搬する、つまりベクトルは下向きが正常であり、これを「胃は降を主る」と言うが、この機能が失えば胃気の向きが逆になる。悪心・嘔吐・げっぷなどが起こる。胃気失和・胃失和降ともいう。 |
| 遺屎(いし) |
| 大便失禁。 |
| 医食同源(いしょくどうげん) |
| 薬食同源(やくしょくどうげん)と同じような意味だが、日本でつくられた造語とされる。ふだんから口にする飲食物も病気の予防や治療には大事だよって言いたいときに使う言葉。 |
| 遺精(いせい) |
| 性行為を行っていないのに精液が漏れること。眠っているときに起こると夢精。 |
| 倚息(いそく) |
| 呼吸困難。何かに寄りかかって息をしている。 |
| 溢飲(いついん) |
| 飲(いん)の病証のひとつ。四肢(手足)や全身の皮下にたまった浮腫(水滞)のこと。 |
| 一貫堂医学(いっかんどういがく) |
| 森道拍が創始した漢方医学。現代人の体質を、瘀血証体質・臓毒証体質・解毒証体質というものに三大分類して治療や体質改善するのが特色で、いわゆる後生派、古方派、折衷派などを超えた独自の位置づけとなっている。 |
| 胃内停水(いないていすい) |
| 胃腸の水分代謝が悪く、胃の中に過剰の水分がある。胃のあたりを軽くたたいたり揺すったりするとポチャポチャと音がする状態。 |
| 遺尿(いにょう) |
| 小便失禁。睡眠中に尿が排出されること。腎虚によるものが多い。 |
| 胃熱(いねつ) |
| 胃が熱をもった状態。食べても食べても空腹感があり過食状態になりやすい。げっぷ、胸やけ、口の渇き、歯肉の腫れ、便秘などがみられる。胃火(いか)とも言う。 |
| 胃痞(いひ) |
| 胃に何かが痞えている感覚。 |
| 異病同治(いびょうどうち) |
| 異なる病気を同じ治療法で治しちゃう。症状が異なっていたとしても、その根本的な原因を追究してみて、すべて同じ原因から起きたと考えられる場合は、同じ治療法でOK。↔同病異治(どうびょういち) |
| 飲(いん) |
| ①水分の代謝異常により生じる病理産物。水液が体の一部分に停滞しているものであり、質が薄くて水っぽいもの。(濃くて粘っこいものは「痰」という。が、区別が難しいときはまとめて「痰飲」と言っておけば間違いない) ②漢方薬の名前の最後に付く言葉。「○○湯」とだいたい同じ。「茯苓飲」「折衝飲」 |
| 陰(いん) |
| ↔陽(よう)。静か、暗い、冷たい、重い、凝集、湿潤、内向き、抑制、衰退といったものの象徴。 |
| 陰液(いんえき) |
| ①体内に存在する津液(しんえき)や血(けつ)など、からだに必要な栄養分を含んだ水液すべて。 ②気・血・津液(水)・精という人体を構成する基本的物質のうち、機能面をあらわす気を「陽気」というのに対比させて、物質面をあらわすときの血・津液・精を「陰液」と呼ぶ。 |
| 飲家(いんか) |
| ふだんから水毒(水飲)のある人。 |
| 咽乾(いんかん) |
| のどの粘膜の乾燥。 |
| 咽喉不利(いんこうふり) |
| のどの異物感や不快感。 |
| 陰虚(いんきょ) |
| ①陰が、弱い・少ない・足りない状態。陽の力が相対的に強いので、熱っぽい、手足がほてる、寝汗をかく、舌が赤くなる、などがみられる。体の構成成分の液体(血・体液など)が不足し、消耗、乾燥状態になる。 ②日本漢方では、陰証(寒がり)で虚証(体力が弱い)の人を指していることがあるので、まぎらわしい言葉の一つ。 |
| 陰虚火旺(いんきょかおう) |
| 陰虚内熱(陰虚による熱症状)の顕著なもの。虚火。陰虚陽亢。 |
| 陰虚内熱(いんきょないねつ) |
| 陰(陰液)が不足したことで相対的に陽(陽気)が増えた状態になり、口の渇きや、手足がほてるなどの熱症状が出ること。虚熱。特に熱症状の強いものを陰虚陽亢と呼ぶ。 |
| 陰証(いんしょう) |
| ①すべての病気を陰か陽に分けようとした場合、虚証・裏証・寒証は陰証に分類する。 ②日本漢方における寒証(寒がり、冷え症)のこと。 |
| 咽中炙臠(いんちゅうしゃれん) |
| のどに炙った肉が張り付いたような異物感がある状態。 咽中炙肉 。梅の種がのどに痞えた感覚(梅核気)と表現されることもある。 現代医学的に言われる咽喉頭異常感症やヒステリー球に相当する。『金匱要略』の半夏厚朴湯の条文に書かれている症状。 |
| 隠痛(いんつう) |
| 我慢できる程度の、激しくはないが慢性的、持続的な痛み。シクシク痛む。 |
| 陰陽(いんよう) |
| ①陰陽学説。陰陽論。中国古代の哲学の一部。互いに関連し合いながらも対立する二つの事柄を総括する。天と地・昼と夜・男と女・明と暗・熱と寒・動と静・興奮と抑制・上昇と下降・亢進と衰退…。一般的ルールでは、明るいもの、活動的なもの、温かいもの、外向きなものは「陽」に、暗いもの、動かないもの、冷たいもの、内向きなものは「陰」に属させる。また、一つの事柄の内部にある、対立する側面を説明することもできる(腎陽と腎陰など)。 ②証を決める八鋼弁証の表・裏・虚・実・寒・熱・陰・陽の8つを、表裏・虚実・寒熱・陰陽の4セットにしたときの一つ。 ③漢方を勉強する者にとっての最初の障害となる複雑な概念。男性の中に女性ホルモンがあるように、陽の中に陰があったりもする。 |
| 陰陽五行説(いんようごぎょうせつ) |
| 陰陽説と五行説を結び付けた理論。東洋医学では、体の構造や機能、病気の進展などの解釈に都合よく用いる。臨床的に用いると混乱することもあるので抽象的な概念として理解するべき。 |
| 印籠(いんろう) |
| 丸薬などを入れて持ち歩く、庶民の携帯用の薬ケース(ピルケース)。江戸時代のファッションアイテム。 |
スポンサーリンク
う
| 運化(うんか) |
| 脾の機能のひとつで、転化と運輸を意味する。飲食物を消化して栄養物質を作り出し(転化)、吸収した栄養物質を全身に送り出す(運輸)。脾は を主る。 |
| 温病(うんびょう) |
| ①温病論として論じられる。清の時代に、急な高熱が出る熱性感染症を中心にまとめられたもの。日本は鎖国をしていて伝わってこなかったせいか『傷寒論』に比べると馴染みが薄い。抗生剤が普及してしまったため現在でもなお馴染みが薄い。有名な方剤に銀翹散など。 ②『傷寒論』にも温病のことは書かれていて、温病の一番の特徴(傷寒との違い)は、発熱と口渇があって「悪寒がない」こと。治療原則としては辛涼解表。 |
え
| 営気(えいき) |
| ①血とともに血管内を巡る、栄養に富む気。脾によって飲食物から作られ、肺から血管に入り、血の成分の一部として全身を養っている。 衛気に対して陰に属する。 ②血液の物質面を「営血」というのに対して、血液の機能面を「営気」として分けることができる。 |
| 衛気(えき) |
| 血管外の全身(細胞間、組織間)を巡る気。脾によって飲食物から作られ、肺の作用によって散布される。体表面からの外邪の侵入を防御する(免疫機能)、汗腺で汗の排泄をコントロールする、臓腑を温めるなどの働きをする。起きているとき体表を巡っている衛気は眠っているときには体内に入るとされ、だから眠るときは代わりに布団をかぶらないと風邪をひきやすい(らしい)。営気に対して陽に属する。 |
| 液(えき) |
| 津液(しんえき)を津と液に分けた場合、サラサラした水が津、ネットリした水が液。関節や髄にある液体。 |
| エキス剤(えきすざい) |
| 生薬を工場で煮出して抽出した成分(エキス)を、乾燥し、添加物を加え、顆粒剤・粉末・錠剤の形に加工しパッケージしたもの。↔煎じ薬 |
| 噦(えつ) |
| 噦逆(えつぎゃく)。通常、吃逆(きつぎゃく)のこと。しゃっくり。しゃくりあげる。 |
| 益気(えっき) |
| ⇒補気(ほき) |
お
| 嘔(おう) |
| 嘔吐において、吐き気がしてオエッという声がでてしまうのが「嘔」。それに実際にモノが吐き出されるときの「吐」。声とモノが両方出れば「嘔吐」。 |
| 黄汗(おうかん) |
| 衣が黄色く染まる汗。 |
| 嘔逆(おうぎゃく) |
| 悪心、むかつきのことを「嘔」として、それの激しいものを「嘔逆」と言う。 |
| 往来寒熱(おうらいかんねつ) |
| ①熱が下がると悪寒がする、悪寒が止むと熱が出る、を繰り返す ②午前は平熱なのに、午後や夕方になると熱がでる、を繰り返す 少陽病のときにみられる症状で、柴胡剤を使用する目標である。 |
| 悪寒(おかん) |
| ぞくぞくとした病的な寒気を感じること。体を暖めても服を重ね着しても布団をかぶっても寒気がする。ふるえをともなうものは悪寒戦慄(寒戦)という。 |
| 瘀血(おけつ) |
| ①巡りが悪い、または流れが停滞した「血」。微小循環障害。 →瘀血を引き起こす原因と、瘀血による痛みの特徴 ②血の滞りのある病態、血行不良のことは血瘀(けつお)と呼ぶが、それと同じ意味で「瘀血」が使われることも多い。例「 ③言うと小さい男の子が必ず笑う言葉。 |
| 御匙(おさじ) |
| 江戸時代の将軍家おつきの医者。漢方医が常に薬匙(調剤用のスプーン)を携行していたことから。 |
| 悪心(おしん) |
| 吐き気。 |
| 悪熱(おねつ) |
| 発熱で、熱感がとくに強いもの。悪寒や悪風は伴わず、熱に悶え苦しむ。服を着ていられないほど体が熱い。『傷寒論』の陽明病にみられる熱。 |
| 瘀熱(おねつ) |
| 裏にこもった熱。尿利の減少を伴う。湿熱。 |
| 悪風(おふう) |
| 風にあたると寒気や不快感を感じること。悪寒の比較的かるいもの。 |
| 温煦(おんく) |
| 温服(おんぷく) |
| 漢方薬を温かい状態で飲むこと。煎じの場合は温かいうちに服用、エキス剤はお湯に溶かして服用。 |
| 温補(おんぽ) |
| 温めて補う治療法。寒証に対して温め、かつ虚証ならば補うのが原則。人参湯、真武湯、四逆湯などは温補剤という。 |
| 温薬(おんやく) |
| 温める作用のある薬。桂皮、乾姜、当帰、細辛など。 |