 漢方薬の解説
漢方薬の解説 【神秘湯】の解説~ストレスで悪化しやすい咳や喘息に用いる漢方薬~
神秘湯(しんぴとう)解説ページです。気を巡らせながら咳を止める効果がある漢方薬で、精神的要素に関連する咳、不安症状が強い方の慢性の咳に使われます。漢方薬生薬の構成の特徴と効果、使用上の注意点を解説します。特に麻黄の配合量が多い点は注意が必要です。
 漢方薬の解説
漢方薬の解説  違い・使い分け
違い・使い分け  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説 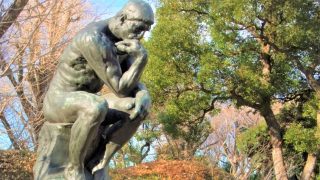 違い・使い分け
違い・使い分け  違い・使い分け
違い・使い分け  漢方薬の解説
漢方薬の解説  違い・使い分け
違い・使い分け  漢方薬の解説
漢方薬の解説  冷えに使う漢方薬
冷えに使う漢方薬  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  漢方薬の解説
漢方薬の解説 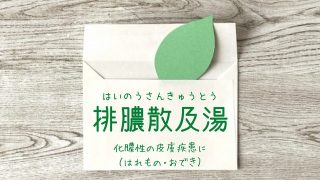 漢方薬の解説
漢方薬の解説 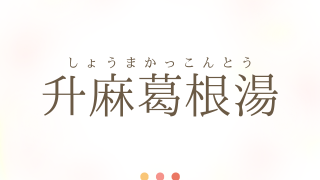 漢方薬の解説
漢方薬の解説 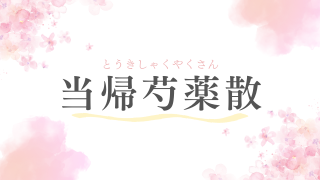 漢方薬の解説
漢方薬の解説