二朮湯(にじゅつとう)の解説
「二朮湯」はなぜ五十肩の薬とされているのか?
また、五十肩以外の痛みには使えないのでしょうか?
実際のところ、二朮湯は五十肩によく適しているのに、肩こりにはあまり使われません。
配合されている生薬の特徴から、二朮湯の効果を解説します。
肩こり⇒肩の筋肉疲労、筋肉痛、つまり筋肉の問題
五十肩⇒肩関節の炎症、つまり関節の問題
適応症
「二朮湯」の添付文書上の効能効果をみてみますと…
医療用エキス製剤(ツムラ)
五十肩
薬局製剤
体力中等度で、肩や上腕などに痛みがあるものの次の諸症:四十肩、五十肩
漢方薬の効能効果というのは非常に幅広く症状が書かれていたりして、いったいどういう漢方薬なのか分かりにくいこともよくあります。
それに比べると二朮湯の効能効果はとても分かりやすい!
いや。でもシンプルすぎませんか?
どうして四十肩や五十肩専用の漢方薬になってしまうのか。
漢方薬でこのように適応が狭いものは非常にめずらしいです。
二朮湯の解説

では、なぜ「二朮湯」の適応が五十肩なのか?
効能書きはシンプルに書かれていますが、構成している生薬は少し多くて複雑です。
これだと構成の特徴がつかめないので、以下のように整理して解説していきます。
- 蒼朮・白朮
- 半夏・陳皮・茯苓・甘草・生姜
- 威霊仙・羗活・香附子・天南星
- 黄芩
では、まず、二朮湯の名前の名前の由来にもなる、2つの「朮」について。
蒼朮と白朮
二朮湯の名前の由来である、二つの「朮」。
だいたいどちらかだけを使うのが一般的な「朮」が、2つとも使用されているのが特徴です。
蒼朮と白朮の違いはここでは割愛しますが、ともに「湿」を解消する薬物です。
湿という邪を取り除くためにわざわざ2つを併用しています。
「湿」を簡単にいうと、体内の「水」が病的なかたちに変化したものです。
これが関節に存在すると、関節痛という症状になります。
最初にヒントで書いたように、
肩こり⇒肩の筋肉疲労、筋肉痛、つまり筋肉の問題
五十肩⇒肩関節の炎症、つまり関節の問題
とすれば、二朮湯の適応症は、関節の中の「湿」が関連する症状なので、
肩こり、筋肉痛よりも、五十肩が適していると考えられます。
逆に肩こりに使われる「葛根湯」(かっこんとう)が五十肩に使われないのは、「湿」を除く作用で劣るからです。
半夏・陳皮・茯苓・甘草・生姜
半夏・陳皮・茯苓・甘草・生姜の部分は実は「二陳湯」(にちんとう)です。
気管支炎や、悪心や嘔吐、食欲不振などの胃の症状に応用されることが多いですが、
漢方的には痰飲(体内に停滞している異常な「水」)を取り除くための方剤です。
一見、悪心・嘔吐に用いる漢方薬は、肩の痛みには関係なさそうに思えますが、
痰飲の発生の源である消化器を治すことによって、湿邪による痛みの発生を抑えようとしています。
つまり、急性の痛みだけではなく、慢性化した症状への配慮ということになります。
五十肩のように慢性的に経過する症状に適しています。
ちなみに、二陳湯に、朮があって、もし、あと人参と大棗を加えたら「六君子湯」(りっくんしとう)になるのですが、人参と大棗には潤す作用があるので、湿を乾かそうとしている作用には反してしまいますので加えられません。
威霊仙・羗活・香附子・天南星
これらは鎮痛効果が期待される生薬です。
威霊仙・羗活は、経絡の湿を乾かし、
香附子・天南星は、上半身の湿を乾かす、と考えられています。
やはり体の上半身の症状に対して効果が出るように意識されて作られた方剤のようです。
香附子には理気作用もあります。
黄芩
黄芩は、炎症を抑え、熱を冷やす、腫れを軽減する効果があります。
また、燥性の生薬が多く配合されるので、乾かし過ぎてしまうことよる熱の発生を抑える効果も期待されているようです。
まとめ

以上をまとめると
主に、
・上半身の症状で
・慢性的な症状で
・関節の「湿」が関係していて
・痛みがある
そんな症状に「二朮湯」の効果が期待できることが分かります。
つまり、五十肩の効能で間違いないことが納得できますでしょうか。
ただし、「朮」が二つとも併用されていることからも、大事な点は「湿」の存在であり
「湿」(水または炎症による浮腫)が関係する痛みということであれば、肩だけに限定されることはなさそうです。
比較的身体はがっちり(もしくは太り気味)だけど、胃腸があまり強くない、
という人の神経痛、しびれなどに用いることができます。
慢性的ではなく、一時的な肩や首の痛みの場合には、独活葛根湯(どっかつかっこんとう)の方が即効性があります。ですが、独活葛根湯は長期服用には向きませんし、胃腸が弱い人には適しません。

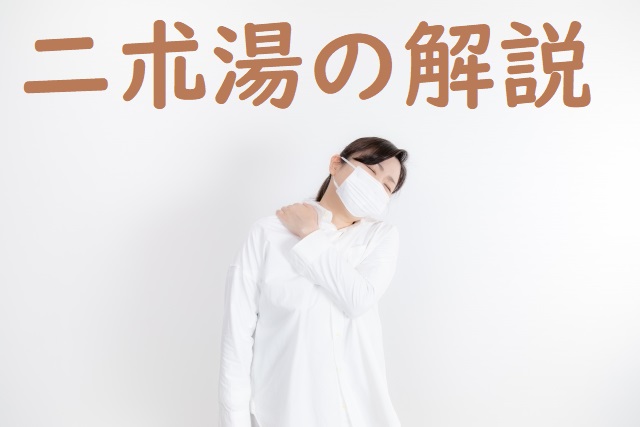


コメント