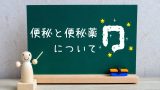便秘の漢方薬|体質から整える自然な排便習慣
「何日も出ないのが普通になっている」
「便意はあるのに、出ない」「出てもスッキリしない」
そんな便秘の悩みを、「年齢のせい」「体質だから仕方ない」とあきらめていませんか?
漢方では、便秘は単なる“腸の問題”ではなく、気・血・水の巡りや体の潤い不足、冷えやストレスの影響など、全身のバランスの乱れによって引き起こされると考えます。
体質に合った漢方薬を用いることで、無理なく自然に出せる身体へと整えていくことが可能です。
荒尾市で便秘の漢方相談をお探しの方へ
便秘の漢方薬は「出ない」だけでなく、硬さ・残便感・お腹の張りといった症状、冷えやストレスなどの要因によっても変わります。
漢方は体質と便秘のタイプを確認して、今の状態に合う方法を組み立てるのが基本です。
漢方薬局 旺樹の杜(熊本県荒尾市)では、来店相談のほかオンライン相談にも対応しており、煎じ薬の全国配送も可能です。
こんなお悩みは、漢方相談の対象になります
- 何日も出ない/出ても少量しか出ずスッキリしない(残便感)
- 便が硬い・コロコロする/切れる・痛い
- お腹が張って苦しい、ガスが溜まりやすい
- 冷えやすい/疲れやすい/食が細い/憂うつ感など、体質面に気がかりがある
- 下剤を続けたくない、合う方法を見直したい
ご相談時に確認すること(より合う提案のために)
- 便の状態(回数・硬さ・量・残便感・腹痛の有無)
- 張り・ガス、冷え/のぼせ、口や肌の乾燥など
- 睡眠・ストレス、食事や水分、運動量
- 服用中のお薬・サプリ(便秘薬、鉄剤、胃薬、向精神薬など)
相談方法(来店・オンライン・配送)
- 来店相談(荒尾市):体質と症状を丁寧に整理し、煎じ薬/エキス剤を含めてご提案します。
- オンライン相談:遠方の方や忙しい方も、自宅からご相談いただけます。
- 煎じ薬の全国配送:ご提案内容に応じて発送対応します(地域外の方もご利用可能)。
相談方法や流れ、連絡手段(LINE・メールなど)は、こちらでご確認ください:
▶ 相談の流れ・予約/お問い合わせ
よくある質問(便秘の漢方相談)
- Q. どのくらいで変化が出ますか?
- A. 体質や便秘のタイプによります。まずは「今の状態を動かす」ことを優先し、安定してきたら「繰り返しにくい体づくり」を段階的に行います。
- Q. 便秘薬(下剤)と併用できますか?
- A. 状況により可能です。併用中のお薬や体調を確認し、負担が出ないよう調整の仕方をご提案します。
- Q. ずっと飲み続けないといけませんか?
- A. 便秘の背景(冷え・乾燥・張り・疲労など)を整えることで、量や内容を見直していくことは可能です。目標を共有しながら進めます。
- Q. 病院に行くべきサインはありますか?
- A. 強い腹痛、血便、急な体重減少、突然の便通変化が続く場合などは、医療機関の受診を優先してください。
- Q. 妊娠中・授乳中でも相談できますか?
- A. 可能です。時期や体調、併用状況を踏まえて安全性に配慮した提案を行います。
便秘は「体質×今の状態」で対策が変わります。
ひとりで抱え込まず、まずは状況、お困りごとをご相談ください。
「毎日出ない」が当たり前になっていませんか?
- お腹が張ってつらいけれど、排便がスムーズにいかない
- トイレに座ってもなかなか出ず、時間ばかりかかってしまう
- 硬くコロコロした便が出ることが多い
- 下剤が手放せなくなり、飲まないと出ない状態になっている
- お腹にガスがたまりやすく、音やにおいが気になり、人前に出るのが不安になる
このような便秘は、年齢や性別にかかわらず、多くの方が慢性的に抱えている症状です。
便通には「出す力(気)」と「潤い(血・陰)」、「めぐる力(気血の流れ)」が必要です。
漢方ではこれらのバランスを整えることで、便秘を体質から根本的に改善することを目指します。
便秘を漢方ではどう捉えるか?
西洋医学では、便秘は「腸のぜん動運動の低下」や「水分吸収の異常」による機械的な問題とされます。
一方、漢方では全身の機能低下や巡りの滞り、潤い不足、心身の緊張状態などが複合的に関係していると考えます。
漢方薬は、ただ腸を刺激して排便を促すのではなく、「自然に出せる力を取り戻す」ことを重視します。
そのため、便秘のタイプを見極め、体質に合った処方を選ぶことが極めて重要です。
必要に応じて下剤との併用を行うこともありますが、最終的には「自然に出せる体質」への移行を目指します。
タイプ別に見る便秘の原因と体質
漢方では、便秘は「実証(余分なものがたまっている)」と「虚証(不足・機能低下)」に大きく分類されます。
誤った処方を選ぶと効果が出ないどころか、腹痛・下痢などの副反応が起こることもあります。
ここでは、代表的な5つのタイプをご紹介します。
① 実熱タイプ(こもった熱・食べすぎ)
体内に熱がこもり、腸内の水分が消耗されて便が硬くなって出にくくなるタイプです。
油っこい物や甘いものの過剰摂取、生活の乱れが背景にあり、口臭や吹き出物、のぼせなども伴います。
② 血虚タイプ(血の不足による潤いの欠如)
血が不足し、腸に潤いが行き届かないことで、コロコロと乾燥した便になります。
顔色が青白く、めまいや立ちくらみ、不眠など血虚の典型的な症状を伴うこともあります。
③ 陰虚タイプ(体の乾燥)
体の内側の潤いが不足している状態で、肌や喉の乾燥、ほてり、寝汗などを伴います。
便は乾燥してカサカサし、排便時の痛みや出しにくさがあります。更年期以降の女性や高齢者に多いタイプです。
④ 気虚タイプ(出す力が弱い)
腸を動かす「気」の力が不足しているタイプです。いきんでも出ない、残便感がある、疲れやすい、冷えやすいなどの症状を伴います。
虚弱体質・高齢者・産後などに多く見られます。
⑤ 気滞タイプ(ストレス・緊張による停滞)
ストレスで気の巡りが滞ると、大腸の動きも不安定になります。
便意はあるのに出にくく、お腹が張って苦しい。精神的な緊張やイライラが強い人に多い傾向です。
その他の便秘に使われる処方例
桃核承気湯:婦人科疾患に関連した便秘や月経前後の便秘に
乙字湯:痔を伴う便秘や硬便に
三黄瀉心湯:イライラや便秘を伴う不眠・のぼせに
桂枝加芍薬大黄湯:腹痛・しぶり腹・腹部膨満などを伴う場合に
大建中湯:冷えによる腹部の不快感、下腹部痛を伴う便秘に
など、「便秘」は非常に多様な体質が関わるため、自分で市販の便秘薬を選ぶのが難しい症状のひとつです。
体質・体調に応じて適した処方をご提案いたします。
便秘解消のための養生アドバイス
便秘の改善は漢方薬だけでなく、生活習慣・食事・排便姿勢といった日々の積み重ねが大きな鍵を握ります。
特に「冷え」「ストレス」「食の偏り」「運動不足」は、腸の働きを著しく低下させる要因です。
以下では、漢方の視点も踏まえた具体的な養生法をご紹介します。
生活習慣の整え方
腸の動きは自律神経と密接に関わっています。規則正しい生活リズムを保つことが、腸内の環境改善につながります。
- 排便習慣をつける:朝の時間にゆとりを持ち、毎日同じ時間にトイレに行く習慣をつけましょう。便意を我慢することは腸の働きを鈍らせる原因になります。
- 朝は白湯と朝食を習慣に:起床後すぐに白湯を飲み、軽めでもいいので朝食を摂ることで、腸のぜん動運動が促進されます。
- 睡眠時間を確保する:夜更かしや睡眠不足は自律神経を乱し、排便リズムにも影響を及ぼします。
- 軽い運動を日常に取り入れる:ウォーキング、ストレッチ、ヨガ、太極拳などは、気血の巡りを良くし腸の働きを活性化します。
- 腹式呼吸やお腹のマッサージを:緊張やストレスを和らげながら、腸の動きを助けてくれる養生法です。
- ストレスケアも忘れずに:ストレスが続くと「気滞(気の停滞)」が生じ、腸の動きが滞るため、休息や趣味の時間も意識的に取り入れましょう。
1日1回の排便にこだわる必要はありません。自分の体調に合った自然なリズムが一番大切です。
排便しやすい姿勢を整える
排便時の姿勢が悪いと、直腸と肛門の角度が鋭くなり、スムーズな排便が妨げられます。
腸の解剖学的な構造を活かす正しい姿勢を意識することで、力まずに出しやすくなります。
- 背筋をまっすぐに保ち、やや前かがみの姿勢に
- 両ひじを太ももの上に置いて、腹筋に軽く力を入れる
- 足元に台を置くなどして、太ももの高さを調整し、排便しやすい角度にする
- 長時間いきむときは、クッションなどを抱えると安定します
腸にやさしい食事のとり方
漢方では、腸の働きを支えるのは「脾胃(ひい)」の力とされます。
冷たいもの・脂っこいもの・甘すぎるものを控え、気血を生み出す食材や腸の潤いを助ける食材を積極的に取り入れましょう。
- 食物繊維を適度に:きのこ、海藻、ゴボウ、根菜類などの不溶性食物繊維と、寒天やオクラ、こんにゃくなどの水溶性食物繊維をバランスよく摂取しましょう。
- 発酵食品を取り入れる:納豆・味噌・キムチ・ぬか漬け・ヨーグルトなどの腸内細菌を整える発酵食品は、毎日少量でも続けて摂ることが重要です。
- 水分をしっかり摂る:朝や食間の白湯、スープ、みそ汁などで体を冷やさず潤す水分補給を心がけてください。
- 香辛料や温性食品で腸を温める:生姜、にんにく、山椒、シナモンなどの温性食材は、冷えによる腸の働きの低下を防ぎます。
- 無理なダイエットは控える:食事制限や偏食は、気血の不足を招き、便秘が慢性化する原因になります。