 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 【活血行気薬】~川芎・延胡索・鬱金(姜黄)・乳香・没薬・三稜・莪朮~
12-(1) 活血行気薬(かっけつこうきやく)こちらは活血化瘀薬の中でも、特に気滞血瘀証(気滞⇒瘀血)に用いられる生薬です。⇒活血化瘀薬(かっけつかおやく)とは?⇒活血涼血薬はこちら(血熱⇒瘀血の場合)⇒活血温経薬はこちら(血寒⇒瘀血の場...
 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 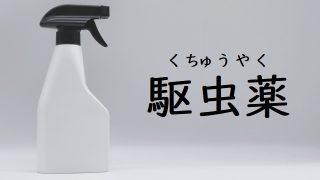 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 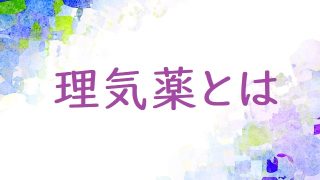 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 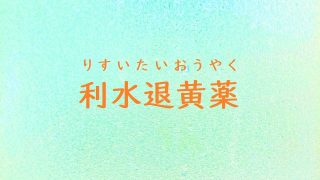 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 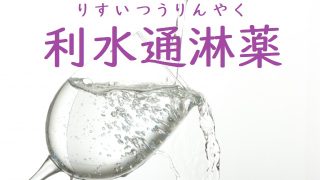 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 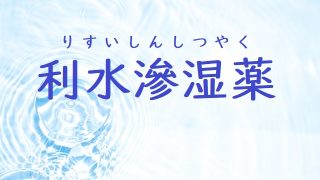 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 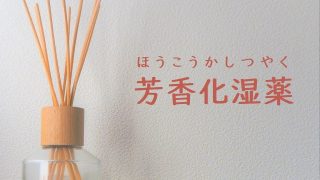 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 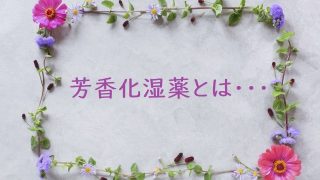 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)