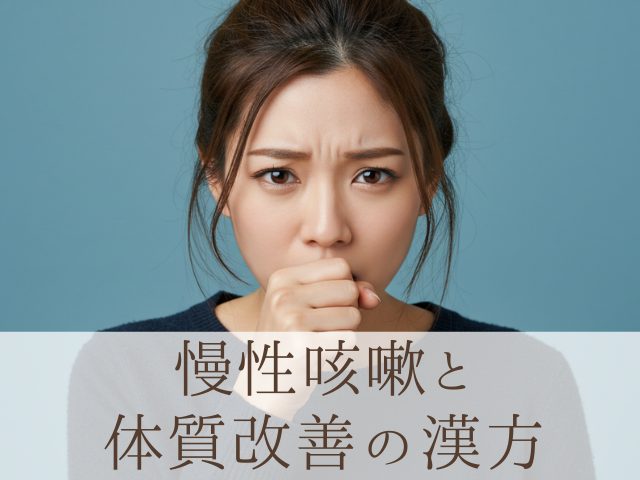咳(慢性咳嗽)の漢方薬
「風邪は治ったはずなのに、咳だけが何週間も続いている」
「夜になると咳がひどくなり、眠れずに困っている」
「検査しても異常はなく、咳止めでもなかなか改善しない」
──長引く咳(慢性咳嗽)に悩む方は決して少なくありません。
漢方では、咳を単なる呼吸器の症状としてだけでなく、体質や臓腑のバランスの乱れを示す重要なサインと捉えます。
漢方医学的にみた咳(外感と内傷)
漢方では、咳は大きく「外感(外からの邪気による咳)」と「内傷(体質や臓腑の失調による咳)」に分けられます。
外感咳嗽
- 風寒・風熱・風燥などが肺を犯して起こる急性の咳。
- 肺の宣発粛降の機能が乱されて咳が起こります。
- 比較的短期間で治まりますが、悪寒・発熱・頭痛などの表証を伴います。
- 主に実証に属します。
内傷咳嗽
- 肺・脾・腎の虚(機能の低下)や気血水の異常が背景にあって起こる咳。
- 咳が慢性化しやすい、もしくは治っても繰り返し起こりやすい。
外感による咳の場合でも、体が虚弱な状態だと「治りきらずに慢性化」してしまうことがあります。
したがって、「現在出ている咳を鎮める」(標治)だけでなく、「咳が続きやすい体質を根本から整える」(本治)ことが重要です。
慢性化しやすい背景──肺・脾・腎
【肺】
肺は「気を主り、宣発粛降を司る」臓。
肺が弱ると呼吸の上下運動が乱れ、咳が長引きやすくなります。
免疫力の低下や、乾燥に弱い体質も関係します。
肺気が不足すると(肺気虚)、息切れを伴います。
体内の水分(津液)が不足し、肺も乾燥すると(肺陰虚)、肺気が上逆して咳がこみ上げます。
【脾】
脾は「痰を生む源」。
脾(胃腸)が弱ると、脾の運化の機能の低下により、水分代謝が悪くなり痰湿が停滞します。
生じた痰湿が肺気の流れを妨げ、咳が悪化します。
もともと胃腸が弱い人だけでなく、食べすぎ飲みすぎでも痰を生じやすくなります。
【腎】
腎は「納気を司る」臓。
腎が弱ると吸い込んだ気を下へ納められず、咳がいつまでも止まらない原因となります。
高齢者や慢性病後に腎虚の症状が多く見られます。
肺と腎の陰虚により、虚熱が津液を濃縮させると、黄色く粘った痰が喉にからみます。
このように、肺・脾・腎の機能が十分に働いていない場合、咳が慢性化しやすくなります。
慢性咳嗽の漢方薬
漢方薬の治療方針の特徴──本治を軸に標治を行う
咳がつらい場合、まずは症状を緩和する「標治」を行います。
しかし、慢性的な咳には、体質を根本から整える「本治」が漢方治療の軸となります。
本治(体質改善)
代表的な漢方薬
肺陰虚:滋陰降火湯
脾気虚:六君子湯・参苓白朮散
腎陽虚:八味地黄丸
腎陰虚:味麦地黄丸
標治(症状緩和)
風寒:
水様の痰・悪寒・頭痛・無汗
→ 麻黄湯/小青竜湯 など
風熱:
黄色い粘った痰・熱感・口渇
→ 麻杏甘石湯/五虎湯 など
燥熱:
乾いた咳・切れにくい痰、鼻や喉の乾燥
→ 麦門冬湯/清肺湯 など
気滞:
ストレスで悪化・胸や脇が苦しい
→ 柴朴湯/神秘湯 など
養生法・セルフケア
慢性の咳を和らげるためには、日常生活の見直しも重要です。
冷たい空気や埃、タバコの煙は咳を悪化させる原因となります。特に冬や乾燥する季節にはマスクを活用して保湿し、室内の湿度も適切に保つことでのどを守りましょう。また、温かい飲み物をこまめに摂ることも効果的です。
食事面では、油っこいものや甘いものは痰を増やし、咳を長引かせる可能性があります。代わりに、はちみつ、大根、れんこん、梨、松の実など、のどを潤す効果がある食材を積極的に取り入れると良いでしょう。
さらに、夜更かしや過労も腎の機能を弱らせ、咳を悪化させる原因となります。十分な睡眠を確保し、軽い運動を取り入れて呼吸を深めることが、回復を早める助けとなります。
まとめ
咳が慢性化するのは、単なる呼吸器の炎症だけでなく、肺・脾・腎の虚が背景にあるためです。
漢方では「本治」を軸に体質を整え、必要に応じて「標治」を行うことで、つらい咳を和らげながら再発しにくい体へ導きます。
あなたに合った漢方薬をご提案いたします。お気軽にご相談ください