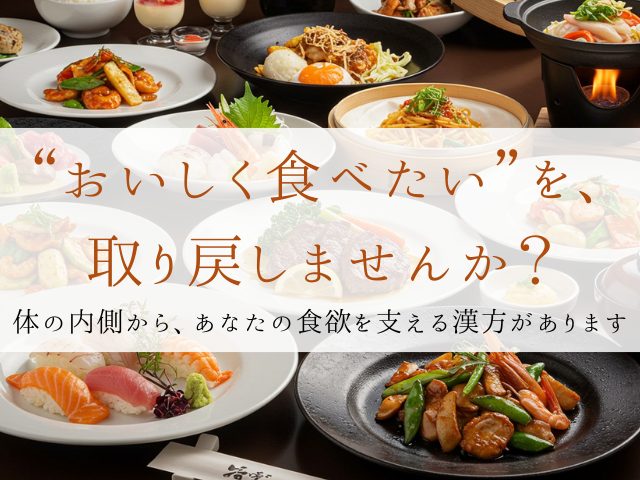食欲不振の漢方薬
「お腹は空いているはずなのに、食べたい気がしない」
「少ししか食べていないのに、すぐに満腹になってしまう」
「体がだるく、食事を作る気力も食べる気力も湧かない」
──そんな“食欲が湧かない状態”は、単なる一時的な不調ではなく、心や体のバランスが乱れているサインかもしれません。
漢方では、食欲不振を「胃腸のはたらきの低下」だけでなく、「気(エネルギー)の巡り」や「ストレスによる自律神経の乱れ」といった全身の調和の崩れとして捉えます。
あなたの体質に合わせた漢方薬で、食欲の回復をサポートします。
「食べたいのに、食べられない」…そんな日々が続いていませんか?
以下のような症状が続く場合は、胃腸の機能や体のエネルギーに何らかの不調がある可能性があります。
- 朝食が食べられず、無理に食べると吐き気や不快感が出る
- 少量の食事でもすぐに満腹感があり、食べ進められない
- 食事の時間になると気分が悪くなる、あるいは食欲がまったく湧かない
- ダイエットもしていないのに体重が徐々に減ってきている
- 胃薬や整腸剤を試しても改善せず、慢性的な食欲低下が続いている
これらの状態は、生活習慣の乱れやストレス、体質的な要因などが重なって生じていることも多く、「全体のバランスを整える」アプローチで改善を目指します。
西洋医学と漢方での見方の違い
西洋医学では、食欲不振の原因として「胃の運動障害」「胃酸分泌異常」「消化器疾患」などが考慮され、薬物療法や栄養指導が行われます。
一方、漢方医学では、胃腸の不調を「脾胃(ひい)」の虚弱や「気(エネルギー)」の停滞、「ストレスによる自律神経の乱れ」などとして全身の状態から捉えます。
そのため、同じ“食欲がわかない”という訴えでも、背景にある原因や体質により使用する漢方薬が大きく異なるのです。
– もともと胃腸が弱く、疲れるとすぐに食欲が落ちる
– ストレスがかかると胃がキリキリする、胸がつかえる
– 暴飲暴食で胃がもたれ、食欲が失われた
– 病後や高齢で体力が落ち、食欲もなくなった
──このように、漢方では「なぜ食欲がわかないのか?」を体質や生活背景から細かく分類し、それに合わせた検討を行います。
タイプ別にみる「食欲不振」の原因と体質
食欲不振は一時的なものから慢性的なものまでさまざまですが、漢方では「脾胃の弱り」「気の巡りの停滞」「熱や湿の停滞」など、いくつかのタイプに分類して考えます。
① 脾胃気虚タイプ(胃腸の虚弱)
胃腸の機能がもともと弱く、疲労やストレスが加わるとすぐに消化吸収力が低下するタイプです。
朝は特に食欲が湧きにくく、無理に食べても胃もたれや眠気が出やすい傾向があります。
また、少量の食事でも消化に負担がかかり、食後に下痢をしたり、体が重だるく感じることも。
このような状態が続くと、エネルギー不足で全身の倦怠感や意欲の低下にもつながります。
舌の色は白く、むくんだように見えることが多いのも特徴です。
② 肝気犯脾タイプ(ストレス・緊張)
ストレスや感情の変化が影響して胃腸に負担がかかり、食欲が落ちてしまうタイプです。
神経質で気分の浮き沈みが大きく、イライラや不安感とともに食欲が低下するケースがよく見られます。
食事の時間になると胸やみぞおちがつかえる感じや、げっぷ・吐き気などが現れることもあります。
このようなタイプでは、ストレスによって「肝」の気が「脾胃(胃腸)」のはたらきを妨げると漢方では考えます。
対応処方例: 茯苓飲合半夏厚朴湯、柴芍六君子湯、安中散、大柴胡湯など
【③ 湿熱・食積タイプ(こもる熱・停滞)】
脂っこいもの・甘いもの・冷たい飲食の摂りすぎにより、胃腸に“湿熱”や“食積”がこもっているタイプです。
消化が追いつかず、胃がムカムカする、食後に膨満感がある、げっぷや口臭が気になるといった症状が見られます。
舌苔が黄色く厚くなるのもこのタイプの特徴で、だるさや体の重さ、眠気を伴うこともあります。
食欲はあるのに食べても満足感がなく、さらに食べてしまうという悪循環に陥ることもあります。
体質に合わせた漢方薬
その他、「食べられない」ときの漢方薬の例
- 小建中湯
…小児や虚弱体質の方で、腹痛をともなう場合に適しています。体を温め、胃腸をやさしく調整します。 - 帰脾湯
…心配事が多く眠れない、気が落ち込みやすい、食べられないといった“心と脾”の両方が疲れているときに有効です。 - 四君子湯
…胃腸のはたらきを底上げします。食が細くやせている方に適しています。 - 十全大補湯
…病後や手術後、長期療養明けなどで体力が著しく落ち、食欲も元気もない場合に用いられます。 - 四逆散
…いつも緊張しやすくストレスにさらされており、胃腸が萎縮して食べられないタイプに適しています。
※体質・体調に応じて適した処方をご提案いたします。
食欲を取り戻すための養生アドバイス
生活の工夫で「気」を整える
胃腸は非常に繊細な臓器で、ストレス・睡眠不足・運動不足・環境の変化などに大きな影響を受けます。
「食欲がない」状態が長引いているときは、まず生活リズムを整えることが第一です。
- 適度な運動(散歩・ストレッチ・軽い筋トレ)は胃腸の動きを促進し、自然な食欲を引き出します。
- しっかりと睡眠を確保し、夜更かしを避けることで自律神経のバランスを整えましょう。
- 食事はなるべく毎日同じ時間にとり、身体に“食べるリズム”を覚えさせることが重要です。
- テレビやスマホを見ながらではなく、落ち着いた環境で食事に集中することで味覚も整います。
多忙な時期や環境の変化(引越し・転職・季節の変わり目など)には、特に胃腸の不調が出やすくなります。無理をせず、心身をいたわるようにしましょう。
胃腸にやさしい食事の工夫
食欲がないときに無理に食べるのは逆効果になることもあります。
まずは「少量でも美味しく、負担の少ない食事」を心がけましょう。
- 一度にたくさん食べるのではなく、小分けにして回数を増やす「分食」がおすすめです。
- 消化の良いもの(おかゆ・煮野菜・白身魚・豆腐など)を中心に取り入れましょう。
- ゆっくり噛むことで胃腸の負担が軽くなり、唾液の分泌も促進されます。
- 冷たい飲食物は胃腸を冷やし、働きを鈍らせるため控えめに。常温〜温かい食事を選びましょう。
- 香りや酸味のある食材(しそ・酢・レモン・梅干し・しょうがなど)は、食欲を刺激する助けになります。
- 見た目や雰囲気も大切です。器や盛り付け、食卓に花や音楽を添えるなど「楽しく食べる」工夫も効果的です。
- 食前に梅酒やワインなど香りのよいアルコールを少量摂るのも、食欲を促す助けになります(ただし体調と相談して)。