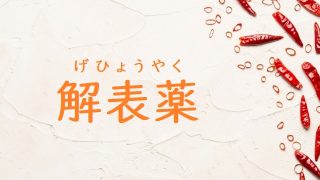 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 解表薬(げひょうやく)の概念
漢方薬に使用される解表薬(げひょうやく)の解説ページです。解表薬とは、体の表面近くにある邪気(じゃき)を発汗によって体外へ発散させる薬です。辛温解表薬と辛涼解表薬の分類、解表薬の応用方法や注意点について解説します。
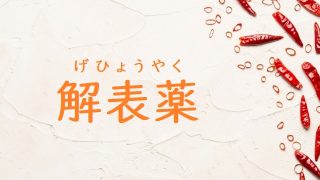 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  漢方薬の服用方法
漢方薬の服用方法  漢方薬の服用方法
漢方薬の服用方法  違い・使い分け
違い・使い分け 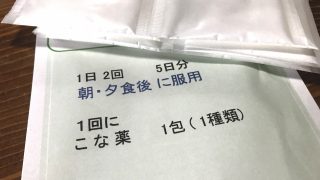 漢方薬の服用方法
漢方薬の服用方法  症状別
症状別  症状別
症状別 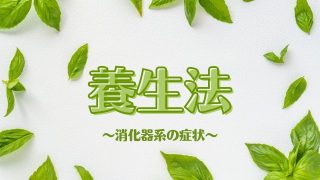 症状別
症状別 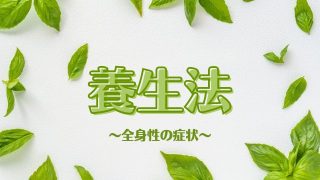 症状別
症状別  漢方薬の解説
漢方薬の解説 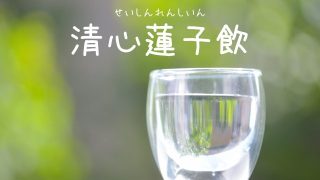 漢方薬の解説
漢方薬の解説  気虚に使われる漢方薬
気虚に使われる漢方薬  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  東洋医学・中医理論の話
東洋医学・中医理論の話  違い・使い分け
違い・使い分け