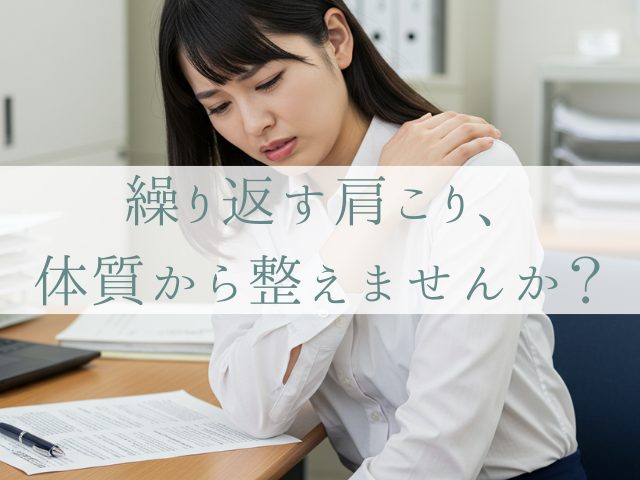肩こりの漢方薬
「肩が重くて夕方には頭痛まで出てくる」
「揉むとその場は楽なのに、翌日にはまた戻ってしまう」
肩こりは多くの方が抱える身近な不調ですが、原因はひとつではありません。長時間の同一姿勢や目の酷使、冷えやストレス、自律神経の乱れなどが重なり、首・肩の筋肉に緊張と血行不良を招きます。
痛み止めやマッサージで一時的に軽くなっても、体の「巡り」やバランスが整っていなければ、再発しやすいのが実情です。漢方は症状の奥にある体質の偏りを見極め、根本から整えるアプローチを行います。
一般的な視点(背景)
西洋医学では、肩こりは筋緊張や血流低下が中心的な要因と考えられます。
パソコン作業やスマホ操作で頭部が前に出る姿勢が続くと、僧帽筋・肩甲挙筋などに負担がかかり、筋肉内の血流が悪化して発痛物質がたまりやすくなります。
さらにストレス下では交感神経が優位になり、末梢の血管が収縮して冷えを助長し、こりを慢性化させます。
したがって、姿勢・環境調整、適切な運動、十分な睡眠といった生活面の修正が、薬物療法と並行して重要になります。
漢方の視点(体質から見た肩こり)
漢方では肩こりを、単に「筋肉が硬い」という局所の問題としてではなく、全身の気・血・水のバランスの乱れが反映された症状と捉えます。同じ“肩こり”でも、背景にある体質(体の状態)によって改善方法が異なります。代表的なタイプを以下にご紹介します。
気滞(きたい)タイプ
精神的な緊張やストレスで気の流れが滞り、肩や首周囲~脇にかけての筋肉に張りやこわばりが現れます。緊張感のある「突っ張る感じ」の鈍痛。月経前や仕事のストレスで悪化しやすく、頭痛や胸脇痛、ため息が増えることもあります。気の流れをスムーズにして、肩の張りを和らげていきます。
瘀血(おけつ)タイプ
血の巡りが悪くなり、肩の周りで鬱血が生じている状態です。肩の同じ部位がいつも固まっている、夜間や冷えると痛みが増す、押したり揉んだりすると強く痛む、というのが特徴です。顔色が暗い、唇が紫がかっている、月経痛が強いなど、他の瘀血サインを伴うことがあります。血流を改善することで、頑固な肩こりがほぐしていきます。
痰湿(たんしつ)タイプ
体内の水分代謝が悪く、余分な湿気がたまることで「重だるい頑固な肩こり」を生じます。むくみや頭の重さ、めまい、胃もたれなどを併発しやすく、雨の日や梅雨に悪化しやすいのも特徴です。冷たい飲食や夜更かしが悪化要因になることも多く、体の中の“湿気”を取り除いて治していきます。
気血両虚(きけつりょうきょ)タイプ
慢性的な疲労や加齢で、体を巡らせるエネルギー(気)と栄養(血)が不足している状態です。肩こりそのものの強さはそこまでではなくても、長引きやすく、同時に全身の倦怠感・食欲不振・立ちくらみを伴いやすいのが特徴です。筋肉を支える基礎体力が不足しているため、補うことで肩の負担を軽減していきます。
まとめ
漢方で肩こりを診ると、「気の流れが滞っているのか」「血流が悪くて硬くなっているのか」「水分の滞りで重いのか」「エネルギー不足で支えられないのか」といった違いが浮かび上がります。これらを見極めて処方を選ぶことで、ただ筋肉を揉むのではなく、再発しにくい体の状態を整えていくことが可能になります。
よく用いられる漢方薬(例)
肩こりは体質に合わせて処方を選ぶことで、同じ「こり」でもアプローチが変わります。以下はあくまで一例です。
気滞には、気の巡りをほどく処方を用います。たとえば加味逍遙散は、張るような肩こりに加えて、いらいらや睡眠の質の低下、月経前悪化が目立つ方に用いられることがあります。精神的緊張が強い場合は、柴胡加竜骨牡蛎湯のように気の昂ぶりと緊張を同時にゆるめる方向を検討します。
瘀血には、滞った血の流れを促す処方が候補になります。桂枝茯苓丸は、しこり感や冷えを伴う慢性的な肩こりに幅広く用いられる代表的な方剤です。刺すような痛みや便秘傾向が強いケースでは、桃核承気湯のように“めぐり”と“下し”を両立させる処方を考えることがあります。
痰湿には、余分な水分の停滞をさばき、頭部のふらつきや重だるさも同時に整えていきます。半夏白朮天麻湯は、めまい・ふらつきと肩こりを併発する方に適することがあり、苓桂朮甘湯は水はけと巡りを助けて、上半身の詰まり感を軽くする狙いで用いられます。
気血両虚には、土台のエネルギーと栄養を補うことが先決です。十全大補湯や人参養栄湯は、疲労感が強く回復が遅い方の慢性肩こりで、体力の底上げを図る目的で使われます。食欲不振に加えて不安や不眠もある場合は帰脾湯も用いられます。
急性の肩こりに用いられる葛根湯について(補足)
肩こりの漢方薬として有名なのが葛根湯、または桂枝加葛根湯です。これらは「風寒(ふうかん)」と呼ばれる外からの冷えや風邪の侵入によって生じる、急な肩や首すじのこわばりに用いられます。悪寒や頭痛、微熱を伴うかぜの初期症状に合わせて処方されることが多く、いわば「かぜ薬」としての側面が強い方剤です。
そのため、日常的に続く慢性的な肩こりに漫然と使う薬ではありません。肩こりが「急に始まったもの」なのか、「慢性的に繰り返しているもの」なのかを見極めることが、漢方では非常に大切です。葛根湯は前者に効果的ですが、後者には体質に応じた別の処方が必要になります
さらに、寝違えのように突然首が回らなくなり、動かすと強い痛みを伴うケースには独活葛根湯が用いられることがあります。これは葛根湯に独活を加え、風寒による急性の筋肉・関節のこわばりに適応する処方です。寝違いの急性期に使う薬であり、やはり慢性的な肩こりに使うものではありません。
急性の肩こりと慢性の肩こり ― 漢方薬の使い分け
| 分類 | 状態の特徴 | 主な症状 | 用いられる処方 |
|---|---|---|---|
| 急性型 (風寒・外因) |
風邪のひきはじめや外気の寒さで突然こりが出る | 首すじの強いこわばり、悪寒、発熱、頭痛、寝違え | 葛根湯・桂枝加葛根湯・独活葛根湯 |
| 慢性型 (体質による内因) |
長期間続く肩こり。再発しやすく生活習慣や体質の影響が強い | 重だるさ、慢性的な張り、冷え、しびれ、疲れやすさ | 気滞・瘀血・痰湿・気血両虚に応じた処方(加味逍遙散・桂枝茯苓丸・苓桂朮甘湯・十全大補湯など) |
関連症状としての五十肩について(補足)
肩こりと混同されやすい症状に五十肩(肩関節周囲炎)があります。
肩こりが主に首や肩周囲の筋肉のこわばり・緊張によって生じるのに対し、五十肩は肩関節そのものに炎症が起こり、動かすと強い痛みを伴うのが特徴です。
特に夜間の痛みや腕を上げられない・後ろに回せないといった動作制限が目立ちます。
漢方では五十肩を「瘀血」や「寒湿」の影響と捉え、血流の改善や関節周囲を温める処方が検討されます。
例えば、桂枝加朮附湯は冷えと痛みを伴うタイプに、二朮湯は関節の痛みが長引き、しびれや動かしにくさを伴う場合に用いられることがあります。
慢性的な肩こりと異なり、炎症や可動域制限が中心の疾患であるため、整形外科での診断・リハビリと併用しながら、漢方で回復を後押しするのが望ましいアプローチです。
生活養生(日常ケア)
回復を早め、再発を防ぐには、日々の過ごし方も大切です。
まずは「温めて、動かす」を合言葉にしましょう。
入浴では首から肩甲骨周囲をしっかり温め、湯上がりにやさしいストレッチで血流を促します。
デスクワークでは、ディスプレイの高さを目線に合わせ、肘・膝が直角になる椅子の高さに調整し、60〜90分に一度は立ち上がって肩甲骨を回す習慣を。
食事は、青魚や黒豆・黒ごまなど“巡り”を助ける食材を意識し、冷たい飲み物の摂り過ぎを控えます。
睡眠は最高の鎮痛薬です。就寝前1時間はスマホを遠ざけ、深い呼吸で交感神経のブレーキをかけましょう。