 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 【袪風湿強筋骨薬】~桑寄生・五加皮~
4-(3) 袪風湿強筋骨薬(きょふうしつきょうきんこつやく)袪風湿強筋骨薬は、風湿の邪をとりながら、筋骨を強める作用もある薬です。湿邪の特徴のひとつが粘滞性で、慢性化するとなかなか治りにくくなるものです。筋骨に侵入した風湿の邪による慢性的...
 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 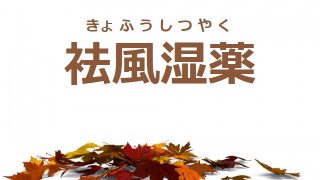 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  生薬の話
生薬の話  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 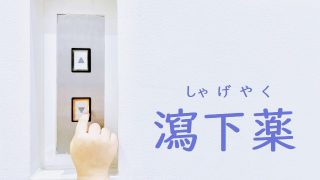 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 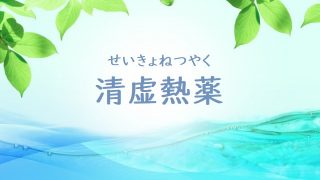 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 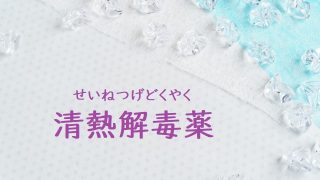 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 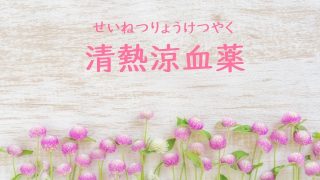 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 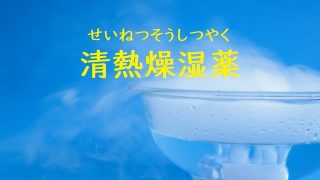 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 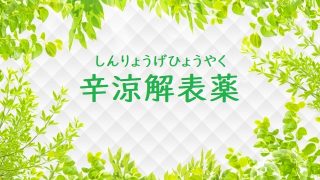 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)