 漢方薬の解説
漢方薬の解説 【柴胡桂枝湯】の解説~やや虚証向きの柴胡剤~
柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)の解説ページです。小柴胡湯と桂枝湯とを合わせたもので、柴胡剤のなかではやや虚証向きの漢方薬です。2つの処方を兼ね備えるので、適応範囲が非常に広い方剤となります。柴胡桂枝湯の特徴と注意点について解説します。
 漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説 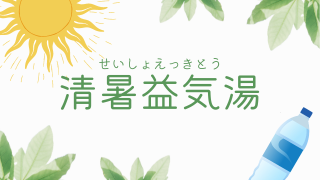 気虚に使われる漢方薬
気虚に使われる漢方薬  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説 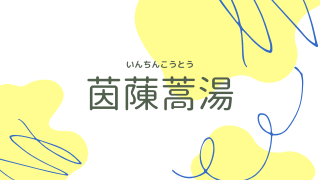 漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説  痛みに使う漢方薬
痛みに使う漢方薬  漢方薬の解説
漢方薬の解説 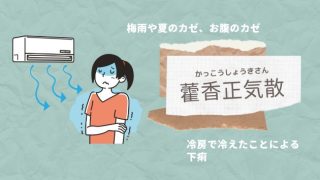 漢方薬の解説
漢方薬の解説