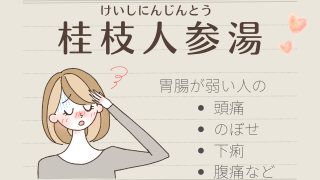 消化器系の漢方薬
消化器系の漢方薬 【桂枝人参湯】~胃腸が弱い人の下痢・腹痛、頭痛に用いられる漢方薬~
桂枝人参湯(けいしにんじんとう)の解説桂枝人参湯けいしにんじんとうは、人参湯に、桂枝(桂皮)を加えたものです。(桂枝湯に人参を加えたものではありません。)身体の内部(消化器)と体表を同時に温める効果があります。胃腸が弱い人、お腹が冷えると下...
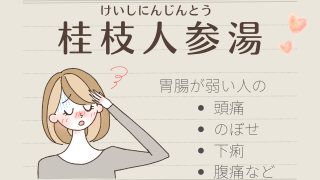 消化器系の漢方薬
消化器系の漢方薬  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説 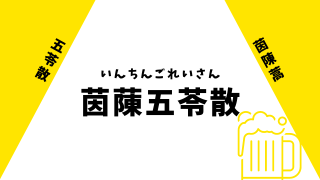 皮膚の症状に使う漢方薬
皮膚の症状に使う漢方薬  婦人科の漢方薬
婦人科の漢方薬  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説 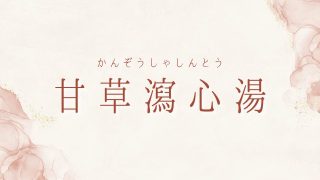 消化器系の漢方薬
消化器系の漢方薬  漢方薬の解説
漢方薬の解説 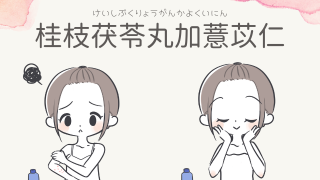 瘀血で使われる漢方薬
瘀血で使われる漢方薬  養生法
養生法 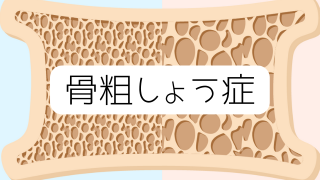 養生法
養生法  腎虚で使われる漢方薬
腎虚で使われる漢方薬 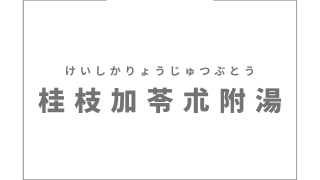 漢方薬の解説
漢方薬の解説 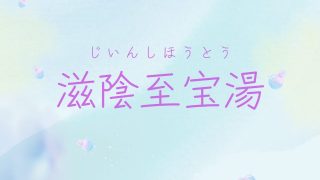 漢方薬の解説
漢方薬の解説