呉茱萸湯(ごしゅゆとう)の解説
呉茱萸湯は、片頭痛に効果がある漢方薬としてよく知られています。
また、呉茱萸湯は、胃が冷えたことに伴う、嘔吐や吃逆(しゃっくり)に対しての漢方薬でもあります。
お腹を温める作用のつよい呉茱萸をメインにして、胃腸のはたらきを改善する生薬が配合されているからです。
「胃の冷え」と「頭痛」は、あまり関係のないように思えるかもしれませんが、
東洋医学的には、胃が冷えるとすぐ横にある「肝」も冷えるため、
肝経の経絡が伸びている頭頂部~側頭部に痛みが起こりやすいと考えることができます。
頭痛の中でもとくに片頭痛の場合は吐き気を伴うことがあり、
冷え・吐き気・頭痛が同時にみられたとき、「呉茱萸湯」はとても有用です。
「味が苦くて飲みにくい」という人もいれば、「平気で飲める」という人もいるのも呉茱萸湯の特徴です。
構成生薬
配合される生薬は4種類で、漢方薬の中ではかなりシンプルな構成です。
この漢方薬の主薬である呉茱萸は、ミカン科の落葉低木、3~5mm程の紫赤色の(未熟な)果実です。
非常に苦い生薬ですが、これが体を温め、痛みをしずめ、吐き気をおさえます。
さらに、脾をおぎなう人参、健胃の生姜・大棗が補助しています。
呉茱萸が配合される漢方薬はそれほど多くはありませんが、
例えば呉茱萸・人参・生姜の組み合わせは、温経湯にもみられます。
作用のポイント

体(とくに腹部)を温める生薬中心に構成されていて、冷え症の人向きの漢方薬です。
普段から、寒さをいやがり、冷たい飲食物を避けていて、暖かい飲食物を好むという人など。
冷えが関係して起こる嘔吐や発作性の頭痛にとくに適しています。
頭痛に対してよく使われますが、頭痛(または片頭痛)に限ったものではありません。
胃腸のはたらきを改善する効果があるので、冷えが原因で、吐き気などの消化器症状が伴うような症状に応用できます。
例えば、月経痛(生理痛)でも使えます。
逆に、熱感があるような頭痛では使えません。
ロキソニンやバファリンなどの鎮痛剤ですぐ胃を悪くする人にも使える、という利点があると思います。
呉茱萸・生姜には制吐作用もあります。
消化器系の症状に対しては頭痛がなくても用いることができます。
効能・適応症状

というわけで、呉茱萸湯は、冷えをともなう↓のような症状に応用されることがあります。
- (吐き気を伴う)片頭痛、習慣性頭痛、神経性頭痛
- 胃が冷えたことで起こる諸症状(胃痛、お腹の張り、食欲低下、吐き気、空えずき、胃酸過多、下痢)
- しゃっくり(吃逆)、呑酸(酸っぱい液が口まで上がってくる)
- 胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃下垂、胃腸虚弱、慢性消化不良症、逆流性食道炎
- めまい、メニエール病、自律神経失調症、過敏性腸症候群
- (吐き気を伴う)月経痛
添付文書上の効能効果
【ツムラ】
手足の冷えやすい中等度以下の体力のものの次の諸症:
習慣性偏頭痛、習慣性頭痛、嘔吐、脚気衝心
【コタロー】
頭痛を伴った冷え症で、胃部圧重感があり、悪心または嘔吐するもの。
吃逆、片頭痛、発作性頭痛、嘔吐症。
【ジュンコウ】【太虎堂】
みぞおちが膨満して手足が冷えるものの次の諸症:頭痛、頭痛に伴うはきけ、しゃっくり
【薬局製剤】
体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するものの次の諸症:
頭痛、頭痛に伴うはきけ・嘔吐、しゃっくり
頭痛に対する即効性
ある漢方薬局では、
頭痛で来局された人で「呉茱萸湯」が合いそうだなと思う人には、問診をはじめる前にまず「呉茱萸湯」を飲んでもらうそうです。
そうすると、問診が終わるころには、もう頭痛は治まっている、という話です。
頓服でも十分効果の期待できる漢方薬です。
注意点
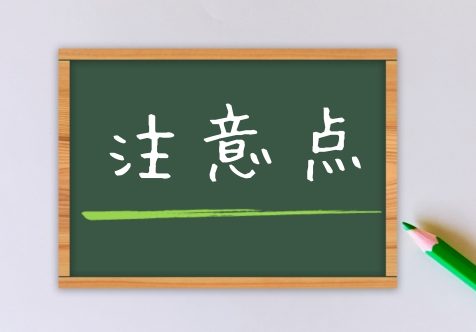
とてもにがい漢方薬として有名です。
煎じ薬の場合は、さらに香りも苦味もキツイかもしれません。
※ただし、呉茱萸湯が合う人の中には「そんなに苦くない」と平気で飲む人もいます。
冷えがあることが大事で、暑がりの人には通常あまり用いられません。
食べ過ぎによる呑酸、二日酔いによる吐き気や頭痛、高血圧による頭痛には適しません。
吐き気、胸やけの症状が強いときは「冷服」、つまり冷たい水で服用した方が飲みやすいです。ただし、冷たすぎると胃をさらに冷やしますので注意してください。
エキス製剤だとそのまま水や白湯で一気に飲みやすいのですが、吐き気のあるときは少量ずつでも構いません。
漢方的な補足解説

呉茱萸湯はとくに偏頭痛のときの漢方薬としてよく知られています。
が、その前に根本的にはまず「胃寒」のときの薬とされます。
胃寒とはつまり胃が冷えたときの症状です。
胃が痛い、食べると吐き気がする、上腹部がつかえる、お腹が張る、などの症状を抑えるための薬です。
確かに配合されている呉茱萸には鎮痛作用があります。
しかし、ただ単に痛みを和らげるということではなく、基本的には、冷えに対しての、温めてあげる目的があることが重要です。
つまり片頭痛などの激しい頭痛に効果があるというだけでなく、冷えたことで症状が悪化する、というのもポイントです。
頭痛のときは、その痛みのせいで、本人もあまり意識が向かないかもしれませんが、お腹だけでなく手や足まで冷えていることがあります。
頭痛に伴って、吐き気や嘔吐がみられることもあります。
このときの吐き気や嘔吐も、漢方的には胃が冷えたことによって起こる症状だと考えられます。
胃の「気」について
「胃」というのは、飲食物を、上から下へ送るのが本来の仕事です。
よって「胃」の「気」の動きは下向きが正常です。
胃が冷えてしまうと、「気」は逆に上へ上がろうとします。
ですから、胃酸が逆流したり、しゃっくりがでたりします。
冷えると消化吸収の機能も弱りますから、胃に水も溜まりやすく、胃が重く、膨満感もあります。
胃の蠕動が弱まるので、胃が食べ物を受け付けなくなり、ムカムカと吐き気も出てしまいます。
そこで呉茱萸湯の、呉茱萸・人参・大棗・生姜の構成は、温めるとともに胃腸機能を高めるものなっています。
胃寒の症状
呉茱萸湯が適する「冷え」のときの症状として。
- 手足やお腹の冷え
- 肩や首すじ~こめかみの凝り(こり)
- 激しい頭痛
- 吐き気(でも吐けない)
- よだれや薄い唾液が多い
- しゃっくり、など。
(すべてが当てはまらなくてもいいです)
吐き気、嘔吐だけならいろいろな原因で起こりそうですが、
涎(よだれ)や唾(つば)がたくさんこみ上げてきて吐きたくなるのも、胃が冷えているときに起こりやすい症状です。
冷えているときは、口渇がありません。
「胃」の冷えと「肝」の冷え
胃と肝の場所は、非常に近い位置にあります。
胃の冷えたときは、肝も冷えます。
肝の気の不足しているときは、さらに冷えが入り込みやすいです。
肝の経絡は、頭部に伸びて、頭頂部~側頭部に及んでいますので、
理論的にも、冷えが肝の経絡に及ぶと、その結果、頭痛(片頭痛)が起こると考えられます。(厥陰頭痛といいます)
そして呉茱萸は、肝経によくはたらく生薬として、呉茱萸湯の主薬になっています。

出典
『傷寒論』(3世紀)
「穀を食して嘔せんと欲すは陽明に属すなり。呉茱萸湯之を主る。湯を得て反て劇しき物は上焦に属すなり」(陽明病篇第243条)
「少陰病、吐利し、手足逆冷し、煩燥して死せんと欲す者は呉茱萸湯之を主る」(少陰病篇第309条)
「乾嘔して涎沫を嘔し、頭痛む者は、呉茱萸湯之を主る」(厥陰病篇第378条)
乾嘔して涎沫を嘔し、頭痛む者、とは→吐きそうだけど食べ物は吐けなくて、唾や胃液ばかりを吐き、頭痛のある者です。
『金匱要略』(3世紀)
「嘔して胸満する者は、(呉)茱萸湯之を主る」(嘔吐噦下痢病篇)



コメント