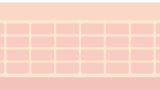アトピー性皮膚炎の漢方薬
〜繰り返す炎症を体の内側から整える〜
「かゆみで眠れない」
「季節の変わり目やストレスで悪化する」
「薬を塗っても再発を繰り返す」
──アトピー性皮膚炎は、皮膚の炎症とバリア機能の低下が重なって起こる、慢性の皮膚疾患です。
漢方では、炎症の有無や体質を見極め、熱・湿・陰陽のバランスを整えることで、かゆみや炎症の再発を防ぐことを目指します。
アトピー性皮膚炎の症状と原因
西洋医学的視点
アトピー性皮膚炎は、もともと皮膚のバリア機能が弱い体質の方に多く見られます。皮膚は外からの刺激や細菌・アレルゲンの侵入を防ぐ役割を持っていますが、この機能が弱まると、わずかな刺激や温度変化でも炎症が起きやすくなります。
また、アトピーでは免疫反応が過剰になりやすく、かゆみや赤みを引き起こす炎症性物質(サイトカイン)が過剰に分泌されます。そのため、症状が悪化すると強いかゆみで皮膚をかき壊し、さらにバリア機能が低下するという悪循環に陥ります。
原因は遺伝的要因だけでなく、ハウスダストや花粉、食物アレルギー、ストレス、生活習慣の乱れなど、さまざまな環境要因が関与します。
漢方医学的視点
漢方では、アトピー性皮膚炎を皮膚に現れた体内バランスの乱れと捉えます。皮膚の赤み・かゆみ・ジュクジュク・乾燥・かさぶたなどの状態を、「熱」「湿」「燥」「瘀血(血の滞り)」といった性質に分類します。
例えば、赤みやほてりが強い場合は「血熱」、ジュクジュクして膿や滲出液がある場合は「湿熱」、乾燥やひび割れは「陰虚」や「血虚」、色素沈着や皮膚の硬化は「瘀血」といった具合です。
さらに、症状だけでなく体質や背景も重要視します。慢性化している場合は、体力や免疫力の低下(気虚)、潤い不足(陰虚)、ストレスによる気の巡りの停滞(気滞)なども考慮します。
そのため、漢方では「炎症の鎮静」+「皮膚の再生力の回復」を同時に行い、再発しにくい状態を作ることを目的とします。
漢方的タイプ分類と処方例
1. 血熱型(炎症が強い)
特徴
皮膚が赤く熱を帯び、かゆみが非常に強いタイプです。掻くと滲出液が出たり、炎症が広範囲に広がったりします。発作的に悪化することも多く、熱感やほてりを伴うことがあります。
漢方的な見方
「血熱」とは、血液に熱がこもって皮膚表面に現れた状態です。この熱がかゆみや赤みの原因となり、さらに掻くことで熱が広がり、悪循環が生じます。まずは熱をしっかり冷ますことが最優先です。黄連や石膏の配合された方剤が有効です。
対応処方例
2. 陰虚火旺型(乾燥・バリア機能低下)
特徴
皮膚が乾燥し、ひび割れや落屑(皮むけ)を伴います。夜になるとかゆみが強くなり、眠れないこともあります。症状は慢性的で、悪化と改善を繰り返す傾向があります。
漢方的な見方
アトピー性皮膚炎は、もともと皮膚のバリア機能が低下している状態です。漢方的に見ると、この「バリア機能の弱さ」は多くの場合陰虚体質に相当します。陰虚とは、体を潤し守る「陰(潤い・栄養・冷却作用)」が不足している状態で、皮膚が乾燥しやすく、外部刺激に敏感になります。
さらに、陰が不足すると相対的に熱(火)がこもり、かゆみや炎症が悪化します。このタイプでは、潤いを補ってバリア機能を高めることと、こもった熱を鎮めることを同時に行う必要があります。
対応処方例
3. 湿潤型(ジュクジュク)
特徴
皮膚が湿っぽく、滲出液や膿、かさぶたができやすい状態です。掻くと症状が広がり、治りにくくなります。
漢方的な見方
「湿」と「熱」が皮膚に滞っている状態で、炎症や化膿を長引かせる原因になります。この場合は湿と熱を取り除き、乾かしながら、かゆみを鎮めることがポイントです。
対応処方例
- 消風散:かゆみ・赤み・湿潤を同時に改善し、皮膚の熱を取り去ります。
- 治頭瘡一方:化膿や湿潤性炎症を抑えます。頭部の症状にも適しています。
4. 脾気虚型(虚弱体質・小児)
特徴
体力がなく疲れやすい、皮膚の回復が遅いタイプです。小児や虚弱体質の成人に多く見られます。
漢方的な見方
「気虚」とは、体のエネルギー(気)が不足している状態です。消化吸収の力が弱く、皮膚の修復や免疫力が十分に働きません。この場合は体力と免疫力を底上げすることが改善への近道です。
対応処方例
タイプ別 養生法(生活・食事)
アトピー性皮膚炎は、漢方薬だけではなく、日々の食事と生活習慣の改善が症状コントロールの鍵となります。バリア機能を守り、炎症を抑え、再発を防ぐために、体質や症状に合った養生を続けることが大切です。
1. 血熱型(炎症が強い)
このタイプでは、体の中に熱がこもりやすく、皮膚表面に赤みや強いかゆみとして現れます。
食事のポイント
香辛料・唐辛子・にんにく・揚げ物・アルコールなど、体を温めすぎる刺激物は避けましょう。代わりに、きゅうり・セロリ・トマト・ゴーヤ・スイカなど体を冷ます食材を意識的に摂ることが有効です。
生活のポイント
入浴はぬるめのお湯にし、長湯を避けます。寝不足や過労は熱を生みやすくするため、十分な睡眠と休養を確保してください。
2. 陰虚火旺型(乾燥・バリア機能低下)
アトピー体質に多く、皮膚の潤い不足と熱感が同時に見られるタイプです。
食事のポイント
冷たい飲食や乾燥した食品(スナック菓子、パンなどの小麦加工品)を控え、黒ごま・くるみ・白きくらげ・山芋・はちみつなど潤いを補う食材を取り入れます。甘い物やアルコールは熱をこもらせ、乾燥を悪化させるので注意。
生活のポイント
過度の運動や長時間の入浴は潤いを消耗するため控えめに。エアコンの風や冬の乾燥から皮膚を守るため、室内加湿と保湿ケアを徹底します。
3. 湿潤型(ジュクジュク)
皮膚が湿っぽく、滲出液や膿を伴うタイプで、湿と熱が滞っています。
食事のポイント
脂っこい料理、甘い物、乳製品は湿を溜めやすいため避けます。代わりに、はと麦・緑豆・冬瓜・もやしなど利湿作用のある食材を積極的に摂ります。冷たい飲み物も湿を悪化させるので注意。
生活のポイント
汗をかいたら早めに洗い流し、皮膚を清潔に保ちます。通気性の良い衣服を選び、湿気のこもらない環境で過ごしましょう。
4. 脾気虚型(虚弱体質・小児)
体力や免疫力が弱く、皮膚の回復が遅いタイプです。
食事のポイント
冷たい飲食や生ものは消化力を弱めるため控え、米・根菜・いも類・鶏肉・白身魚など消化に優しく栄養価の高い食材を中心にします。特に朝食は抜かず、温かい食事で一日のエネルギーを補給しましょう。
生活のポイント
夜更かしや過労は免疫力を低下させます。小児や虚弱体質の方は特に規則正しい生活リズムを守り、無理な運動は避けることが大切です。
まとめ
アトピー性皮膚炎は、薬だけでは改善しきれないことが多く、食事と生活の見直しが再発予防の最重要ポイントです。炎症を冷ます、潤いを補う、湿を取り除く、体力を高める──それぞれの体質に合わせた養生を続けることで、皮膚の状態は安定しやすくなります。