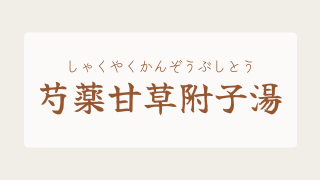 漢方薬の解説
漢方薬の解説 【芍薬甘草附子湯】~冷えを伴う筋肉の痛みやけいれんに用いる漢方薬~
芍薬甘草附子湯(しゃくやくかんぞうぶしとう)の解説ページです。芍薬甘草湯に附子を加えたもので、各種の痛みやけいれんがあって、とくに冷え症または冷えを伴っている場合に用いられる漢方薬です。効能効果、使用上の注意点などについて解説します。
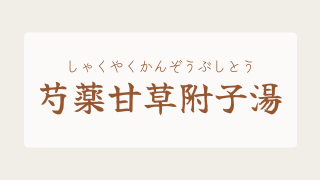 漢方薬の解説
漢方薬の解説 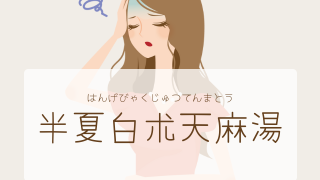 体質改善の漢方薬
体質改善の漢方薬  漢方薬の解説
漢方薬の解説  痛みに使う漢方薬
痛みに使う漢方薬 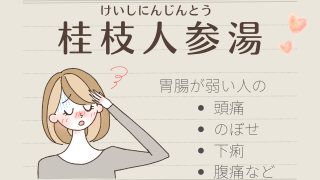 漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説  泌尿器系の漢方薬
泌尿器系の漢方薬  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 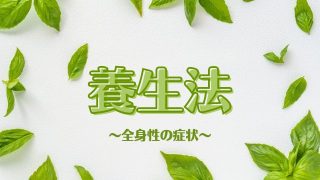 症状別
症状別  皮膚の症状に使う漢方薬
皮膚の症状に使う漢方薬  漢方薬の解説
漢方薬の解説  冷えに使う漢方薬
冷えに使う漢方薬