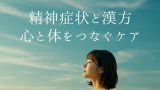不安・緊張(不安障害・過緊張)の漢方
大事な発表の前に緊張する。将来を考えて不安になる。
それは人間であれば誰にでもある自然な心のはたらきです。
けれどもその不安や緊張が強すぎたり、長く続いたりすると、動悸や胸のざわつき、眠れない夜、体のこわばりといった心や体の不調を引き起こすことがあります。
「また不安になったらどうしよう」と新たな不安が重なり、悪循環に陥ることも少なくありません。
漢方から見た「不安」と「緊張」
漢方では、不安や緊張は心(しん)と肝(かん)の働きと深く関わると考えます。
不安と「心(しん)」
心は精神活動の中心で、気や血、陰に養われて安定します。
– 心気虚:気が不足して落ち着かず、不安が生じる、動悸や息切れを伴う
– 心血虚:血が足りず心を養えず、不眠・夢が多い・不安感が強い・驚きやすい
– 心陰虚:潤いが不足し、動悸や焦燥感を伴う・些細なことも不安になる
心が十分に養われないと、安心感を失い不安が強まりやすくなります。
緊張と「肝(かん)」
肝は気血の巡りと感情のコントロールを担います。
– 肝鬱:気の滞りがあり、刺激に対して過敏になりやすく緊張や不安感が高まる
– 肝火・肝陽上亢:気が上に昇り、過緊張のほか、動悸・のぼせ、頭痛、怒りっぽさが出やすい
– 肝血虚:血が不足して肝を養えず、つねに筋のこわばり緊張している状態が続く
肝の気がスムーズに巡らないと、過剰な緊張につながります。
心と肝の関係
心は神志をつかさどり、肝は疏泄をつかさどる。
ともに精神情志の活動と関係しますので、心と肝は互いに影響し合います。
肝気が滞れば心は落ち着かず不安が強まり、心が血を失えば肝を養えず緊張が増す。
この悪循環が、不安や過緊張を慢性的に繰り返す背景にあります。
他の体質との関わり
さらに、腎陰が不足していて心の陰血を滋養することができないといった心腎不交(心と腎の連携不足)があると、不安で落ち着かなくなり、焦り、不眠、多夢、動悸などを伴いやすくなります。
不安や緊張は「気持ちの持ち方、性格の問題」だけではなく、体のバランスの乱れから現れるものでもあります。
不安・緊張に用いられる漢方薬の一例
漢方薬は症状名ではなく体質に合わせて選びます。代表的な処方を挙げると──
- 桂枝加竜骨牡蛎湯:神経過敏で些細なことが気になる、不安・動悸・不眠を伴うときに
- 四逆散:ストレスで肝気が滞り、過度に不安や緊張が続くときに
- 抑肝散:神経の昂ぶりや怒りっぽさを伴い、気持ちが安定しないときに
- 半夏厚朴湯:喉のつかえ感・胸苦しさ・吐き気や嘔吐を伴う不安や緊張に
- 酸棗仁湯:心身ともに疲労、心血虚による疲れているのに眠れない、不安や動悸に
- 帰脾湯:心脾両虚で全身の疲労・貧血・食欲不振を伴い、不安が長引くときに
同じ「不安・緊張」でも、体質によって選ぶ方剤は異なります。専門家にご相談ください。
養生の工夫
朝の光を浴びることは体内時計を整え、心と肝のリズムを回復させます。
深呼吸や散歩など軽い運動は、滞った気を流し体のこわばりを和らげます。
食事ではナツメや百合根など心を安らげる食材を取り入れるとよいでしょう。
そして「気持ちを言葉にして外に出す」ことも大切です。話すこと自体が肝の疏泄を助け、不安や緊張を少しずつ軽くしてくれます。
まとめ
不安や緊張は誰にでもある自然な感情ですが、心や肝の働きが乱れると必要以上に強まり、生活を苦しめることがあります。
漢方は、不安や緊張を生みやすい体質を整え、心と体のバランスを回復させることで安心と安定を取り戻します。
「不安が軽くなれば、また前向きに頑張れる」──そのための一歩を、一緒に探していきましょう。