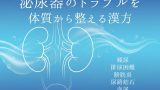膀胱炎の漢方薬
「排尿時にしみるように痛い」
「尿が濁る」
「治ってもまた再発する」
膀胱炎は女性に多い尿路感染症で、抗生物質で一時的に落ち着いても、数週間から数か月のうちにぶり返す方が少なくありません。
西洋医学では大腸菌などの細菌が尿道から膀胱に侵入することで炎症が起こるのが膀胱炎です。尿道が短い、排尿を我慢しやすい生活習慣、冷えやストレス、ホルモンバランスの変化などが再発のしやすさのベースにあります。
漢方では膀胱炎を「淋証(りんしょう)」として捉えます。膀胱の内側に“湿熱(しつねつ)”がこもると、痛みや残尿感、尿の濁り・血尿が現れます。
再発を繰り返す方の場合は、単に炎症を抑えるにとどまらず、体質面からのアプローチが重要になります。
具体的には気虚(免疫・抵抗力の低下)、腎虚(泌尿機能の土台の低下)、そして肝鬱気滞(ストレスによる気の停滞)が重なると、炎症が鎮まりにくく再燃しやすい状態が続きます。
漢方が補うポイント
急性膀胱炎は細菌感染が原因で、発熱や背部痛が強い場合は腎盂腎炎の可能性があり、速やかな受診が必要です。抗生物質は原因菌に対して有効です。
再発しやすいという体質に対しては、
「膀胱の防御力」と「排尿・水分代謝」の部分、すなわち炎症の熱をさます(清熱利湿)とともに、体質を補い、再発しにくい土台をつくる──ことを得意とするのが漢方薬です。
また、検査をしても細菌感染が認められないのに膀胱炎様の不快な症状が続くものにも、漢方薬を使用することができます。
体質別にみる膀胱炎
漢方では膀胱炎のように排尿痛、残尿感、不快感を伴うものを「淋証(りんしょう)」に分類します。一般的な急性の膀胱炎では、膀胱に「湿熱(しつねつ)」がこもることで、排尿痛や残尿感などの症状が現れると考えます。
ただし、膀胱炎を繰り返す方は単なる湿熱だけではなく、腎虚・気虚といった体質的な面(虚証)も背景にあります。
湿熱(しつねつ)
排尿時痛がはっきりし、尿が濁る・におう・残尿感が強いタイプです。下腹部に熱感や張りを自覚することもあります。炎症の勢いを鎮める清熱利湿の方剤が中心になります。
気虚(ききょ)
疲れやすい、風邪をひきやすい、だるさが抜けないといった背景があり、膀胱炎を繰り返します。膀胱を「締めて押し出す力」も弱く、尿がうまく切れません。基礎体力と防御力を立て直す補気の漢方薬を併用して、再発を防ぎます。
腎虚(じんきょ)
加齢や慢性疾患、過労などで泌尿器系の機能の低下し、夜間頻尿や腰のだるさを伴います。冷えが強ければ腎陽虚、ほてりや口渇、寝汗が目立てば腎陰虚の傾向があります。膀胱炎が慢性化しやすく、炎症を鎮めるのと同時に腎を補う養生が不可欠です。
肝鬱気滞(かんうつきたい)
ストレスや緊張で尿意が急に強まり、痛みも増幅します。自律神経の乱れが波をつくり、膀胱の機能が過敏になっています。気の巡りを整える処方を併用することで症状が改善します。
代表的な漢方薬と使い分け
猪苓湯(ちょれいとう)は、残尿感や尿の濁り・排尿困難を伴う膀胱炎の基本処方です。利水と清熱を同時に行い、膀胱の違和感、不快感を和らげます。
五淋散(ごりんさん)は、痛みが強く、血尿や明らかな濁りを伴う急性期から、抗菌薬を服用して細菌がいなくなったにもかかわらず不快な症状が続く場合まで、幅広く適します。湿と熱の勢いを速やかに引かせつつ、腎気を養います。
竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)は、排尿時に熱感や強い刺激感があったり、尿の色が濃く匂いが気になる場合に有効です。陰部の痒みや不快感に対しても使われます。肝胆の熱と、下焦の湿熱を清めます。
再発を繰り返す方には、清熱利湿に加えて体質からの立て直しを行います。疲れやすい・食後にだるいといった方には補中益気湯で気を補い、防御力を回復させます。
ストレスで悪化しやすい場合は清心蓮子飲で心腎を養い不安・緊張を鎮める、あるいは逍遙散・柴胡加竜骨牡蛎湯などで気の滞りを整えることを検討します。
慢性化し、夜間頻尿や冷え・腰のだるさを伴うなら、八味地黄丸や牛車腎気丸で腎を補い、炎症の再燃しにくい下地を作ります。腎陰の消耗が前面に出る方には六味地黄丸を検討します。
糖尿病で膀胱炎を繰り返す場合も、腎虚の傾向がありますので漢方薬がよく用いられています。
間質性膀胱炎について
細菌感染による膀胱炎と異なり、検査で菌が検出されないにもかかわらず、慢性的な頻尿や膀胱の痛みが続くのが間質性膀胱炎です。
原因はまだ明確ではありませんが、膀胱粘膜の障害や自律神経の不調、免疫の異常が関わると考えられています。
漢方では、間質性膀胱炎を「虚実錯雑(きょじつさくざつ)」と捉え、炎症を鎮める清熱利湿と同時に、腎虚・気虚・気鬱などを考慮して、膀胱の粘膜環境を改善を図ります。
長期にお悩みの方ほど、体質の全体像を把握することが重要です。
再発を止めるための生活養生
- 冷えは大敵。下腹部・腰を温める習慣を
- こまめに水分をとり、尿をためすぎない
- アルコール・香辛料など刺激物を控える
- ストレスをためない。自律神経の乱れは再発要因に
- 免疫力を高める生活(睡眠・栄養・休養のバランス)
まず、尿を溜め過ぎないことが基本です。そのためにはこまめに水分をとって排尿する、膀胱内に菌を滞らせない習慣が、薬効を後押しします。
就寝前の過度な水分は控えつつ、日中は適量を分けて摂取し、利尿のリズムを整えましょう。
下腹部と腰を冷やさない衣類選びや、適温での入浴は、腎陽を守り再発を抑制することにつながります。
辛味・アルコールなど刺激物は炎症期には避け、回復期も量を控えめに。
ストレスが再発の引き金になりやすいため、深呼吸やウォーキングなど、自律神経を整える習慣も役立ちます。

まとめ
膀胱炎は単なる細菌感染ではなく、湿熱・気虚・腎虚・肝鬱気滞といった体質的要因が関わっています。
抗生物質や、漢方薬の清熱剤で急性期を乗り切ることは有効ですが、胃腸が弱い方や冷え症の方では長期利用がかえって体調を崩すこともあり、体質改善との併用が欠かせません。
また、菌が検出されない間質性膀胱炎のような慢性疾患にも、漢方的なアプローチが役立つ場合があります。
「繰り返す」「慢性的に治らない」といった膀胱のトラブルは、ぜひ体質から整える視点でのご相談をおすすめします。