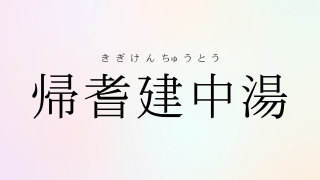 漢方薬の解説
漢方薬の解説【帰耆建中湯(きぎけんちゅうとう)】の解説
帰耆建中湯(きぎけんちゅうとう)の解説ページです。小建中湯に当帰と黄耆を加えたもので、虚弱体質の改善、病後や術後の体力回復、ねあせ、化膿性皮膚疾患に用いられる漢方薬です。配合される生薬のはたらき、効能効果、使用のポイントについて解説します。
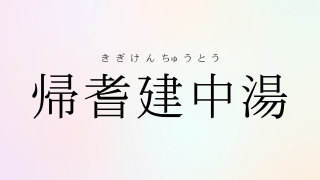 漢方薬の解説
漢方薬の解説 皮膚の症状に使う漢方薬
皮膚の症状に使う漢方薬 漢方薬の解説
漢方薬の解説 漢方薬の解説
漢方薬の解説 漢方薬の解説
漢方薬の解説 血虚で使われる漢方薬
血虚で使われる漢方薬 漢方薬の解説
漢方薬の解説 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能) 漢方薬の解説
漢方薬の解説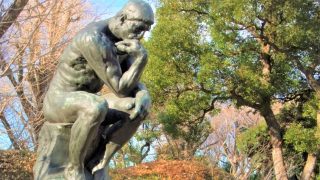 違い・使い分け
違い・使い分け 漢方薬の解説
漢方薬の解説 かぜ(感冒)に使う漢方薬
かぜ(感冒)に使う漢方薬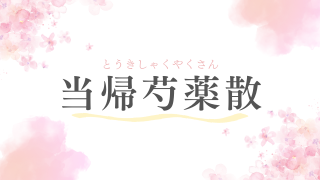 漢方薬の解説
漢方薬の解説 漢方薬の解説
漢方薬の解説 漢方薬の解説
漢方薬の解説