『傷寒論』第6条
第2条で、太陽病の中風、
第3条で、太陽病の傷寒、がありました。
そして、太陽病にはもう一つ、温病があります。
傷寒であれば、風寒のような寒の性質の邪による病です。
対して温病であれば、風熱のような熱性の邪による病です。
傷寒と温病の違いを認識しておきましょう、というのが第6条です。
ちょっと長い条文ですので、ポイントだけまとめておきます。
第6条
読み方⇒
太陽病、発熱して渇し、悪寒せざる者は、温病となす。
もし発汗しておわり、身灼熱する者は、名付けて風温という。
風温の病たる、脈陰陽ともに浮、自汗出で、身重く、睡眠すること多く、鼻息すればかならず鼾し、語言出で難し。
もし下を被るものは、小便利せず、直視し失溲する。
もし火を被る者は、微なれば黄色を発し、劇すれば即ち驚癇の如く、時に瘈瘲す。
もし火にてこれを薫すれば、一逆してなお日を引き、再逆は命期を促す。
意味⇒
太陽病で、発熱して口が渇き、悪寒のしない者は、温病である。
もし発汗して、身体がとても熱い者は、風温という。
風温の病とは、陰陽の脈がともに浮で、自然に汗が出て、身体がだるく、ぼんやりとしていて、鼻呼吸すればいびきをかき、話すことも困難である。
もし誤って下剤を使えば、小便が出にくくなり、目が障害され、失禁する。
もし誤って火熱の治療を行えば、軽症であれば皮膚は黄色くなり、重症の場合は精神が錯乱したような、痙攣を時に起こす。
このような誤った治療を一度行えば、治癒までの日数を遅らせ、繰り返し誤った治療を行ったときには寿命を縮めてしまいます。
傷寒(しょうかん)と温病(うんびょう)の違い
傷寒論と温病論とは、実は別々に論じられていて、2本立てで考える必要があるのですが、
日本においては、傷寒論に比べて、温病論の方はあまり馴染みがありません。
傷寒論の第1条に、太陽病の症状として、「悪寒がする」ことが述べられています。
それに対して温病の一番目の特徴は、発熱と口渇があって、「悪寒がない」ことです。
実際、ゾクゾクと悪寒のするカゼではなくて、喉が痛くなって悪寒がないまま急に高熱がでるようなカゼに、麻黄湯や葛根湯などを使っていても全く効果はありません。
症状が違うということは、その原因も違います。間違った治療法をしていれば、回復が長引いてしまうだけでなく、逆に症状を悪化させてしまうこともあります。
条文の後半には、間違った治療は寿命を縮める、と恐ろしいことまで書かれいます。
| 病因 | 熱感 | 悪寒 | 頭痛 | 口渇 | 脈 | 治療 | |
| 傷寒 | 寒邪 | ○ | ◎ | ○ | × | 浮緊 | 辛温解表 |
| 温病 | 温邪 | ◎ | △ | △ | ○ | 浮数 | 辛涼解表 |
温病は、熱性の邪気なので、体の水分を消耗しやすい病です。
さらに下剤やら、体を温める薬やらを投与し続けるのは、間違った治療となります。
まとめ
例えば現代でもようやく、ウイルス性のカゼに抗生剤を使っても意味がないことが知られてきましたが、
白血球数やCRPの検査などによって適切な治療薬を選ぶように、
当時、検査機器がない時代であっても、傷寒と温病の違いをしっかり意識して適切な治療を行おうとしていたことが分かります。

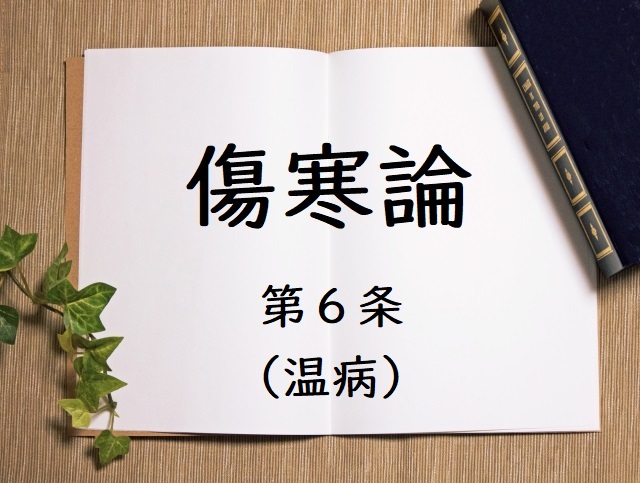

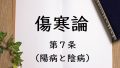
コメント