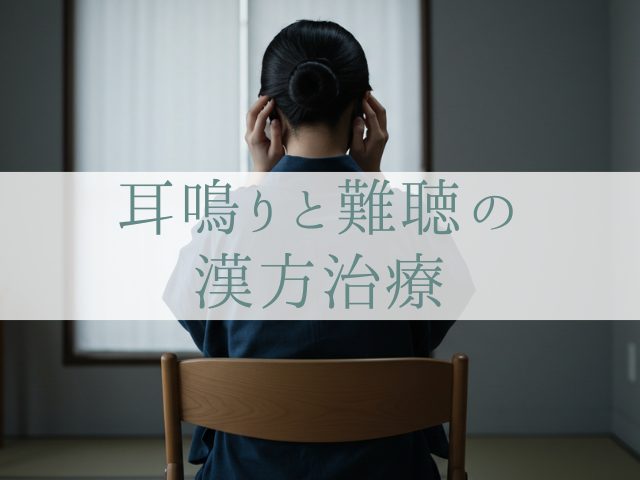耳鳴りの漢方薬
「キーンと高い音が響き続けて集中できない」
「耳鳴りが気になって眠れない」
「病院では『加齢のせい』と言われてしまった」
──そんな耳鳴りに悩む方は少なくありません。
一般的に耳鳴りは、耳の何らかの障害で起こることが多いですが、それ以外にも精神的ストレス、自律神経の乱れ、高血圧、糖尿病など、さまざまな影響で現れることもあります。
漢方ではとくに、老化だけでなく全身の体質的なものとしてとらえ、改善の糸口を探ります。
耳鳴りと難聴の関係
耳鳴りは、耳の中で実際には音が存在しないのに「音を感じてしまう状態」です。
「ジージー」と蝉が鳴くような音、「ブーン」というモーターのような低音、「ピー」「キーン」という高音の電子音や金属音、聞こえ方は様々です。
- 加齢による聴力低下(加齢性難聴)
- 騒音による内耳障害
- 突発性難聴・メニエール病の後遺症
- 血流障害や薬剤の副作用
などが関わります。
耳鳴りはしばしば「難聴」と結びつきます。
聴力が落ちると、脳は「音が不足している」と感じ、勝手に信号を増幅しようとします。その結果、実際にはない音を耳鳴りとして認識してしまうのです。
つまりその点では、耳鳴り=耳や脳の“過敏な反応” とも言えます。
「腎は耳に開竅する」
漢方医学的には「腎は耳に開竅(かいきょう)する」とされ、耳の働きは「腎」の状態と密接に関係しています。
腎の精(生命エネルギー)が充実していれば聴覚ははっきりしますが、
加齢のほか、過労、生活の不摂生、慢性疾患による体力低下などによって、腎が虚してくると、耳鳴りや難聴が生じやすくなります。
また、耳鳴りには腎だけでなく「肝」「脾」の影響も関わります。
肝:気や血の流れを調整。ストレスで乱れると「肝火上炎」により耳鳴りが悪化。
脾:飲食物から気血水を作り出す。脾が弱ると痰湿が生じ、耳の通りが悪くなる。
つまり耳鳴りは、腎虚を中心に、肝や脾の機能低下・気血水の乱れ が複雑に関わっていると考えられます。
耳鳴りの体質タイプと特徴
耳鳴りは体質ごとに特徴が異なります。
1. 腎虚タイプ
- 加齢や慢性疾患による「腎精不足」
- 難聴の低下、ジーンと蝉の鳴くような音が続く慢性の耳鳴り
- 腰や膝のだるさ、ふらつき、頻尿、足腰の冷えを伴う
2. 肝火上炎タイプ
- 疲労やストレス、怒りなどで「肝気」が上昇
- キーンと高い音が突然強く鳴る。突発性の難聴が起こることも。
- のぼせ、頭痛、イライラ、口の乾燥や苦みを伴う
3. 痰濁タイプ
- 暴飲暴食など食事の不摂生や、脾胃(胃腸)の弱りで痰湿が停滞
- 痰湿が熱と結びつき突き上げると、耳が詰まったようにボーッと強い耳鳴りが起こる
- めまい、ふらつき、吐き気、頭重感を伴うことが多い
4. 気血両虚タイプ
- 耳や脳を滋養するための気血が不足
- 疲労によりジワジワと耳鳴りが続く
- 倦怠感、顔色不良、立ちくらみ、動悸、息切れなどを伴う
耳鳴りに使われる代表的な漢方薬
腎虚タイプ
- 六味丸(六味地黄丸)
腎陰を補う。夜間の耳鳴り、不眠、手足のほてりを伴う耳鳴りに。 - 八味地黄丸
腎陽を補う。慢性的な耳鳴り、冷え、腰のだるさ、夜間頻尿を伴う場合に。 - 滋腎通耳湯
腎陰と肝血を補う。聴力の低下、のぼせ、めまいを伴う耳鳴りのほか、ストレス性の耳鳴りにも。
肝火上炎タイプ
- 加味逍遥散
高音の耳鳴り。ストレスや緊張で耳鳴りが強くなる場合に。 - 竜胆瀉肝湯
イライラや怒りっぽさ、顔面の紅潮・目の充血、口が苦いなどの熱証が強いとき。
痰濁タイプ
気血両虚タイプ
養生法・セルフケア
耳鳴りの改善には、漢方薬だけでなく日常生活の工夫も欠かせません。まず大切なのは、規則正しい睡眠を心がけることです。夜更かしや不規則な生活は「腎精」を消耗させ、耳の不調を悪化させてしまいます。十分な休養をとり、体の回復力を守ることが大事です。
また、ストレスのコントロールも重要です。強い緊張や怒りは「肝火」を高め、耳鳴りを一層強くしてしまいます。深呼吸や軽い運動、趣味の時間を取り入れるなど、自分なりのリラックス方法を持つことが役立ちます。
さらに、耳や首まわりを温めて血流を良くすることも効果的です。ネックウォーマーを使ったり、蒸しタオルやカイロを耳の後ろにあてたり、首や肩をほぐす軽いマッサージを行うことで、耳周囲の血流が改善し、症状が和らぐことがあります。
食生活では、過度な塩分やアルコールに注意すること。香辛料などの刺激物、カフェインは神経を興奮させる作用があり、耳鳴りを悪化させることがあるため症状のあるときは控えることをおすすめします。
このように、日常のちょっとした工夫が耳鳴りの改善に役立ちます。生活を整えながら、体質に合った漢方薬を取り入れていくことで、より確かな改善を目指すことができます。
まとめ
耳鳴りは「歳のせいだから仕方ない」とあきらめてしまう方が多いですが、漢方では腎・肝・脾のバランスを整えることで改善を目指すことができます。
一人ひとりの体質に応じて漢方薬を選ぶことで、耳鳴りの不快感や難聴の進行を和らげるサポートが可能です。