 漢方薬の解説
漢方薬の解説 【滋陰降火湯】~切れにくい痰、咳、口腔乾燥に用いられる漢方薬~
滋陰降火湯(じいんこうかとう)の解説滋陰降火湯じいんこうかとうは、身体に潤いを与える(⇒滋陰)、それによって、上昇する熱症状を抑える(⇒降火)という漢方薬です。うるおい不足による、切れにくい痰、咳、口腔乾燥などに用いられています。構成生薬に...
 漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説 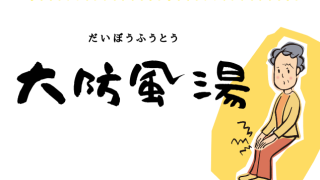 冷えに使う漢方薬
冷えに使う漢方薬  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説  漢方薬の解説
漢方薬の解説  中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  生薬の話
生薬の話 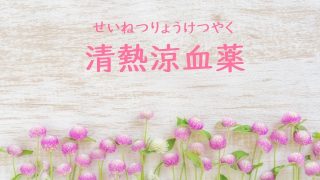 中薬学(生薬の効能)
中薬学(生薬の効能)  漢方薬の解説
漢方薬の解説 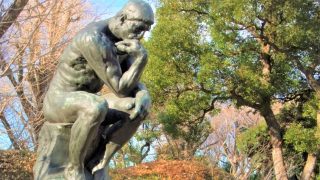 違い・使い分け
違い・使い分け  漢方薬の解説
漢方薬の解説  泌尿器系の漢方薬
泌尿器系の漢方薬  漢方薬の解説
漢方薬の解説